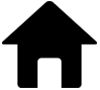令和元年10月25日大阪高裁逆転無罪判決(傷害致死 揺さぶり疑い)
主文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
第1 控訴趣意等
本件控訴の趣意は、主任弁護人我妻路人、弁護人秋田真志、同正木幸博、同高山巌、同辻亮及び同川上博之連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官海津祐司作成の答弁書及び答弁書(補充)に記載のとおりである。また、本件では、当審において事実取調べが行われているところ、これを踏まえた弁護人の弁論は、前記主任弁護人作成の「弁論」と題する書面に、検察官の弁論は、検察官石垣光雄作成の「弁論要旨」及び「弁論補充書」と題する各書面に、それぞれ記載のとおりである。
論旨は、要するに、訴訟手続の法令違反及び事実誤認である。
当裁判所は、記録を調査し、当審での事実取調べの結果をも併せて検討した結果、控訴趣意中、事実誤認の論旨には理由があり、その余の控訴趣意について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れないとの結論に達した。以下、その理由を説明する。
第2 原審の審理及び判決の概要
1 公訴事実
本件公訴事実の要旨は、被告人は、平成28年4月6日(以下、月日のみの記載は平成28年の出来事であり、時間のみの記載は4月6日の出来事である。)午後2時20分頃から同日午後4時50分頃までの間に、大阪市a区内のマンションの一室(被告人の娘であるAの自宅。以下「本件マンション」という。)において、Aの次女であるB(当時生後2か月。)に対し、その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え、よって、Bに急性硬膜下血腫、くも膜下出血、眼底出血等の傷害を負わせ、同年7月23日、大阪府高槻市内の病院において、Bを前記傷害に起因する脳機能不全により死亡させた、というものである。
2 原判決の判断構造
原審は、公判前整理手続の結果、Bが上記傷害により死亡したこと、Bの受傷原因が外力によるものであることは、争いのない事実と整理し、争点は、被告人が、Bの頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えたか否かであるとした。
そして、審理の結果、硬膜下血腫、脳浮腫、網膜出血が生じた機序が、頭部を揺さぶられるなどして回転性の外力が加わることにより生じたもの、いわゆるSBS(Shaken Baby Syndrome、揺さぶられっ子症候群)であるとされ(このように診断する考え方を、ひとまず「SBS理論」と呼ぶことにする。)、これを前提に、Bが受傷した時間帯に、Bと一緒にいてBにそのような外力を加えられた(加害行為)可能性がある者は、被告人とBの姉(当時2歳2か月)のみであり、Bの姉による加害が否定される以上、本件の犯人は被告人以外にはいないと認定した。すなわち、Bの症状が、SBS理論により、回転性の相当強い程度の外力によるものとされ、それを前提に、その時間帯に、そのような外力を加えることが可能な者を消去法的に特定すると、犯人は被告人しかいないというのである。
3 原審の審理の概要
原判決の判断構造が、前記のようなものになった経過として、原審の審理の概要をみておく。
本件は、裁判員裁判対象事件であり、前記公訴事実を巡り、公判前整理手続において、主張と証拠の整理が行われた。
原審弁護人は、当初から、被告人はBに対して何らの暴行を加えていないとして、公訴事実を争っていた。そして、公判前整理手続の初期段階においては、Bの症状の原因がSBSによるとの原審検察官の主張についても、専門医に当たって検討した形跡がうかがわれる。しかし、その結果、Bの症状が外力によるものであることについては争わないということになった。原審弁護人は、いわゆる犯人性のみを争い、これに付加して、高齢者である被告人の体格や体力からすると、検察官が主張する、頭部を揺さぶるか又はそれと同程度の急加減速をかけるという外力を加えることは極めて困難であること、被告人以外の者による犯行可能性として、Bの姉が、Bの髪の毛を掴んで上下に揺さぶるなどしていたこと、公訴事実記載の時間帯に被告人がBに暴行を加える状況はなく、被告人には動機もないことなどを主張した。
これらを受け、原審裁判所は、前述したように争点を整理し、これに沿って公判廷において、書証、人証が取り調べられた。その中には、小児科を専門とするC医師(以下、医師の名は、2回目以降は姓で特定し、その公判供述は「○○証言」のように記載する。)や法医学の教授であるD医師の証人尋問も含まれていた。
4 原判決の内容
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、本件公訴事実と同旨である。
原判決は、C医師及びD医師の各供述等に依拠して、〔1〕Bは、急性硬膜下血腫、多発性のくも膜下出血、びまん性脳損傷に続発した脳浮腫、両目の広範囲にわたる多発多層性網膜出血等の傷害を負い、その頭部外傷等の重症度に鑑みると、受傷直後から意識障害に陥り、その後は、母乳を飲んだり、泣いたりすることができなかった、〔2〕Bの受傷原因は、硬膜下血腫等を引き起こす内因性の病態が確認されないことから、外因によるものであり、局所的な受傷ではないこと等に照らし、Bの傷害は、頭部を揺さぶられるなどして回転性の外力が加わることにより生じたもので、その外力の程度は、5cmの振り幅で1秒間に3往復揺さぶるといった、成人が全力で揺さぶる程度の強い衝撃を受けて受傷したものである、〔3〕Bの受傷時期は、被告人が本件マンションを訪れた平成28年4月6日午後2時20分頃から、その後Aが帰宅した午後4時50分頃までの間である、〔4〕この時間帯に、Bの頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えることのできた人物は被告人以外にはいない、などと認定し、被告人の年齢や体格等を踏まえても、被告人がそのような暴行を加えることが著しく困難であるとは認められないとして、結論として、被告人がBに暴行を加えて死亡させた犯人であると認定し、被告人を懲役5年6月に処した。
第3 事実誤認の論旨の具体的内容(当審における争点)
1 原審の事実認定の判断枠組み等は前記のとおりであるが、弁護人の事実誤認の論旨は、その判断枠組み自体に疑問を投げかけるものであった。症状の原因が外力によるものという、原審では前提とされていた点に疑問が提起されたのである。
すなわち、論旨は、Bが死亡するに至った真の原因は、外力ではなく、脳静脈洞血栓症であり、少なくともその合理的な疑いが残るにもかかわらず、原判決は、脳静脈洞血栓症の可能性を何ら検討することなく、SBS理論に依拠したC医師、D医師の証言のみを根拠に、被告人による揺さぶりが原因であると断定しており、他の証拠を一切無視した原判決の事実認定は、論理則・経験則に反するもので、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある、というのである。
2 所論を、若干具体的に示しておく。
所論は、症状の原因が外傷であるとすると、Bが病院に搬送された直後の血液検査のデータ(後に詳しく検討するPT-INRやフィブリノゲンの数値)は、説明がつかないか、または、説明が非常に困難であるとして、症状の原因が外傷であるという前提が誤りである可能性が高いと主張する。そして、可能性として、Bの症状の原因は、内因性の脳静脈洞血栓症やこれによって引き起こされたDIC(播種性血管内凝固症候群)である(少なくともその合理的な疑いが残る)と主張する。その根拠としては、〔1〕病院に搬送された直後のBの血液データ(PT-INR値、フィブリノゲンの数値)、〔2〕CT画像、〔3〕Bの症状と、整合していることを挙げる。また、〔4〕Bの治療経過も脳静脈洞血栓症の発症と矛盾しない、〔5〕脳静脈洞血栓症、DICにより、くも膜下出血が生じた可能性も否定できない、〔6〕仮に硬膜下血腫が生じていたとしても、脳静脈洞血栓症によって生じた可能性は否定できない、〔7〕網膜出血、胞状網膜剥離も、脳静脈洞血栓症、DICが原因と考えて矛盾しない、〔8〕脳浮腫も、脳静脈洞血栓症によって生じたとして説明できる、としている。
第4 当裁判所の判断
1 当裁判所の審理の概要と結論
当裁判所は、本件において、Bの症状の原因が外力、すなわち、外傷によるものであるのかという本件の根幹に関わる事項について、内因性の疾患という新たな可能性が指摘されたことは、本件の結論を大きく左右する極めて重大な問題であると認識し、記録を調査の上、控訴審が事後審であるとはいえ、事柄の性質上医学的専門的な見地からの検討が中心になることも踏まえ、原判決が前提とした点から検討し直すこととし、必要な証拠調べを行った。
具体的には、弁護人の所論を踏まえ、弁護人が請求した、脳神経外科を専門とする医師2名(E医師及びF医師)、脳神経内科を専門とする医師1名(G医師)の証人尋問、検察官が請求した、小児科を専門とする医師(原審でも証言しているC医師)の再度の証人尋問等の事実の取調べを行った。
その結果、医学的にみて、Bの症状の原因が、所論のいう内因性の脳静脈洞血栓症等である可能性を否定できない(少なくともその合理的な疑いが残る。)から、原判決は、その事実認定の前提(Bの症状は外力によるものである。)において、誤っている可能性があり、この点のみでも、原判決の事実認定は大きく揺らいでいる。念のため、原判決が外力によると認定した根拠についても検討したが、外力によるものと認定できるだけの基礎的事情を認めることはできず、さらに、Bが体調の異常を来したとされる当時の状況を検討しても、被告人がBに対し、Bの死亡に結びつくような暴行を加えたことを積極的に推認できるような状況は見当たらない。
結局、被告人による暴行を認定した原判決は、論理則、経験則に照らして、不合理といわざるを得ず、事実を誤認したものであって、この誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れない。
2 当裁判所の認定する前提事実(Bの症状と治療経過)
事実誤認の論旨の検討に当たり、証拠によって明らかに認められる、本件前後のBの症状と治療経過を以下に示す。
ア Bは、平成28年▲月▲日に誕生し、出産前後を通じた検査や検診で、異常を指摘されたことはなかった。本件当日の4月6日も、未明の授乳時まではいつもどおりであったが、午前6時か午前7時頃の授乳時は飲みが悪く、授乳後いつもは頬を触ると笑うのが全く笑わず、午前11時頃、午後2時頃、いずれの授乳時も飲みが悪かった。これら3回の授乳は、いつも40分のところが20分くらいであった。
イ 被告人は、日頃から、しばしば本件マンションに孫の顔を見に行くなどしていた。本件当日も、Aが銀行に行くというので、その間Bらの面倒を見るためもあって、午後2時20分頃に本件マンションを訪ねた。外出予定のAに代わって、被告人がBを抱き上げ、ゲップをさせようとしていたが、Bは咳き込んだ後、いつもと同じような泣き方で泣いており、被告人は、泣き止まないのでベッドに寝かせてくると言って、Bを抱いて寝室に行ったが、行く途中かそのあたりで、急に泣き止み、目をつぶったため、ベビーベッドに寝かせた後の、午後3時16分頃、Aは外出した。
ウ Aは、外出先から3回にわたって被告人に電話を掛けてきて、買い物について相談するなどした。午後4時48分頃、Aが帰宅し、洋室で被告人と20分間くらい雑談をした後、午後5時過ぎ頃、寝室にBの顔を見に行くと、ベビーベッドで、いつもの体勢で仰向きに寝ていたが、呼吸がおかしく、顔色が悪く、白くなっていた。午後5時29分頃、Aは、姉に電話をかけて、Bの顔色や呼吸がおかしいから、病院へ連れて行ってほしいと依頼し、午後5時38分頃、H病院に、「子供の息が変なんです」という電話を架けた上で、姉の運転する車で、帰宅したBの父とともに同病院に向かった。
エ 午後6時35分頃、H病院に到着し、午後6時43分頃、救急外来を受診し、顔面蒼白、下顎呼吸をしている状態で、速やかに挿管、人工呼吸管理、蘇生が開始された。血液検査の結果、著明なアシドーシス及び高血糖が認められたが、インスリンは投与されなかった。血の酸性度は、正常値がPH7.4のところ、PH6.9であった。全身の初期検査を実施したところ、心臓がほとんど動いておらず、今にも止まりそうな状態であったため、心臓に関してより高度な医療が行えるIセンターに転院することとなった。
オ 午後8時15分頃、Iセンターに救急搬送されて到着し、直ちに小児循環器集中治療室に入院し、血圧は安定していたが、導尿すると膀胱から出血し、気管内からも出血を認めた。血液検査(詳細は下記のとおり)でもDICの診断で、治療を開始した。心臓超音波検査を実施したところ、心臓の大きさや形は正常であり、心臓の拡張や心臓の筋肉が厚くなったりする異常は認められず、心筋症を疑う所見はなかった。強心剤を投与したところ、心臓の動きは急速に良くなり、血液の循環が回復し、翌4月7日朝頃までには、心臓の動きは正常に近い状態まで回復した。
血液検査の結果は、次のとおりである。搬送後間もない、午後8時34分に実施された血液検査では、PT(プロトロンビン時間)が10未満(小児の基準値は70~100)、PT-INRが測定不能(正常が1で、数字が大きくなる(延長する)ほど血が固まりにくくなっていることを示す。8を超えると測定不能となる。小児の基準値は0.75~1.15。)、フィブリノゲンが50未満(小児の基準値は200~400、新生児は低値で150~340)など、凝固系の検査項目で異常値を示しており、DICの状態であった。DICの抗凝固療法として、午後8時56分にヘパリンNaを、午後9時52分に新鮮凍結血漿を、午後11時4分にリコモジュリンを、午後11時45分にノイアートを、それぞれ投与する治療を行い、これらの治療により、午後10時58分の血液検査では、フィブリノゲンが50未満は変わらなかったが、PT-INRが2.78に改善し、4月7日午前1時32分の時点でも、DICは継続しており、血尿も継続していたが、同日午前2時57分の血液検査では、PTが59、PT-INRが1.35、フィブリノゲンが100と更に改善し、同日午前6時56分の血液検査では、PTが80、PT-INRが1.11、フィブリノゲンが154とほぼ正常値になった。その後も、同日午前8時45分に新鮮凍結血漿を、同日午後零時10分にヘパリンNaを、同日午後10時にリコモジュリンを、午後10時43分にノイアートをそれぞれ投与しているが、同月8日午後零時22分には、血性尿から通常尿へ変化傾向が見られ、同日午後零時54分、同月9日午前11時30分の2回、ヘパリンNaの投与で終了した。PT、PT-INR、フィブリノゲンなどは、同月7日午後9時33分、同月8日午前6時56分の血液検査では、正常値になっている(当審検16、17)。
一方、Bは、入院当初より瞳孔が散大し、対光反射を認めず、針で刺しても体を動かさなかったことから、4月7日午前2時過ぎ頃、頭部CTを撮影したところ、カルテには「皮髄境界不明瞭、脳実質周囲に高輝度あり、脳浮腫とくも膜下出血を疑う」(午前2時55分、J医師、小児循環器科)、「脳浮腫、くも膜下出血、左側脳室出血あり」(午前3時4分、K医師、小児循環器科)と記載があり、脳浮腫、くも膜下出血、左側脳室出血が確認された。
カ Bの眼科所見については、4月8日、眼科のL医師が診察し、両眼網膜出血、両眼胞状の網膜剥離の所見(両眼底の後極部に胞状の網膜剥離と周辺部網膜出血。丸で囲み、斜線部が網膜剥離、周囲の点が点状の網膜出血を表す。)が認められ、同月15日、同医師の診察で、両眼硝子体混濁(出血)の所見が認められた。
キ 4月21日、前記眼科所見で網膜剥離、網膜出血が認められたことがきっかけで、外部医師の意見を聞くことになり、MセンターのN医師が訪れて診察し、揺さぶられっこ症候群(SBS)が強く疑われる旨の診断を受けた。
ク 6月15日、Bは、O病院に転院したが、その時点で、既に脳の機能が完全に失われており、自発呼吸はできず、人工呼吸器を使って呼吸している状態であった。
同日、小児科の医長、担当医のP医師の依頼により、頭部から首にかけての部分のMRI検査が実施された。
同月16日、眼科のQ医師が診察し、両眼硝子体混濁、左眼網膜剥離が確認され、硝子体混濁は眼底出血の痕と診断された。
7月23日午前3時17分、Bは、同病院において心臓が停止して死亡した。
3 当審で取り調べた医師の見解
(1)E医師、F医師の見解
ア E医師は、当審において、以下のとおりの意見を述べた。
Bの頭蓋内出血について、脳静脈洞血栓症によって引き起こされた病態である可能性は否定できないとし、その原因は、DICと呼ばれる非常に出血しやすい状況が背景にあり、頭の中に血の固まりができてしまって、血液がうっ滞することによって、弱くなってしまった血管から出血をおこしたのではないかと推論し、Bに脳静脈洞血栓症が発症していた可能性の主な根拠について、以下のとおり説明した(第2回公判E医師の証人尋問調書4、7頁。以下、E医師については、「E、公判回数-頁数」の順で、「E2-4、7」のように示す。なお、他の医師については、姓と頁数のみを示す。)。
〔1〕血液データとの整合及びその後の治療経過と矛盾しないことについて
Bは、血液検査の数値上、PT(プロトロンビン時間)とフィブリノゲンの数値が極端な値を示していたことや、挿管時の出血等、血が非常に出やすい状況であったことなどから、重度のDICであった。頭部外傷の場合、PT-INR値は通常2を超えることはないが、Bは測定不能(8を超えると測定不能)になるぐらい振り切れている状況であったのが外傷とは合わず、BのDICは、内因性の方が可能性は高いと思われる。
頭部外傷では、脳の中の血管に小さな血栓が一杯でき、そのことによって、凝固因子がちょっとだけ消費されることによって、PT-INR値が若干上がるが、2を超えるというのはまれであるのに対し、Bは測定不能であることから、そういう小さな血栓ではなくて、もっと大きな何か凝固因子を大量に消費するような病態が存在しているということになる。また、血液を固める物質であるフィブリノゲンは、血がどこかで固まり始めると消費され、血液中のフィブリノゲンは下がってくるが、通常200を超えているものが、Bは50未満であり、非常にたくさんのフィブリノゲンが使われたと受け止められる値である。
恐らく、静脈洞に最初小さな血栓が出来て、それが雪だるま式に重なっていき、血が固まるのに必要な要素が消費されてDICになった、すなわち、脳静脈洞血栓症が先にあって、DICが引き続き起こされたと推測される(E2-15~18)。
原因疾患に対する治療は、その後3か月間行われていないが、何らかのストレスによって血栓が急に生じるという悪い病気が起こったものの、ある程度病態が落ち着いてストレスがなくなるような状況になると、一見正常なレベルまで落ち着くと考えられる(E2-40)。
〔2〕CT画像との整合について
画像上、上矢状静脈洞に非常に白く三角形に写っており、脳静脈洞血栓症によって形成された血栓(デンスクロットサイン)が写っている可能性がある(E2-7~9)。
〔3〕Bの症状との整合について
脳静脈洞血栓症は、症状として、意識障害、呼吸障害、頭蓋内出血等が起こる可能性があるとされており、搬送された当日、Bに見られた、ミルクの飲みが悪かった、咳をしていた、搬送時に呼吸がおかしかった、意識障害があり、心臓の動きがおかしかったといった症状は、脳静脈洞血栓症の症状と矛盾はない。脳静脈洞血栓症がいつ発症したのかについては、血栓というのは雪だるまのように膨れてくるということが病態として考えられるので、比較的早期に病態が進行してしまって、このような状況になったということであれば、1日以内でもこういう病態が起こることは、理屈の上では可能と考えられる(E2-5、10、11)。
イ F医師は、当審において、E証言の上記見解に対応する内容として、大要、以下のとおりの意見を述べた。
Bの頭部CT画像を詳細に検討すれば、単純に頭部外傷による頭蓋内出血と断定することはできず、内因性の疾患、非外傷性の頭蓋内出血の可能性が大いにあるとし、その主な根拠について、以下のとおり説明した。
〔1〕血液データとの整合及びその後の治療経過と矛盾しないことについて
先に脳静脈洞血栓症が生じ、雪だるま式にそこに血栓が大きくなっていくときに、血液を固める凝固因子が全部そこで消費されてしまうので、PT-INR値が測定不能、フィブリノゲンが50以下という数値になっている。重症頭部外傷でも凝固線溶系の数字は乱れるが、これほど激しく数字が壊れるということは、頭部の単独外傷では通常は起こり得ない。早期から血栓症を溶かす薬であるヘパリンを投与することによって、脳静脈洞血栓症の固まりが溶ければ、回復傾向へ向かっていく(F15、16)。
〔2〕CT画像との整合について
脳静脈洞血栓症の場合には、大脳鎌や小脳テントそのものが肥厚、厚くなって、そこに血液がうっ滞する、もしくは血栓が生じるということが大切な所見であり、Bの場合にも、そのような所見がある(F4、6~9)。
〔3〕Bの症状との整合について
Bが脳静脈洞血栓症を発症した原因は不明である。小児の脳静脈洞血栓症について、13%から18%は原因不明であるとされている文献もあり、Bも原因不明であることが特段おかしな状況ではない。当日の3回の授乳時の飲みが悪いくらいで、脱水により脳静脈洞血栓症まで急激に病態が悪化する可能性はゼロではないし、その場合、それが原因で、くも膜下出血や呼吸障害まで至る、急激な変化をすることも、脳静脈洞血栓症が画像上の程度までひどかったら、十分あり得る(F21、24)。
(2)C医師の見解
これに対し、C医師は、当審において、以下のとおりの意見を述べた。
〔1〕血液データとの整合及びその後の治療経過と矛盾しないことへの反論
血液データとの整合について、頭部外傷の事例で、PT-INRが2を超えるのはまれであるとE医師は証言したが、虐待による頭部外傷で、鑑定書を書いた事例14例のうち、DICレベルで凝固系に異常を来し、PT-INRが2を超えていた事例は4例あった(C38)。
その後の治療経過について、CT画像でE医師が指摘した部分が脳静脈洞血栓症の血栓であれば、広範囲に存在した血栓が、わずか1.5日の抗凝固療法で完全に溶けてなくなってしまうといったことは医学的にはあり得ない。1.5日の治療で、血管の中の血栓が全て溶けて基礎疾患がなくなったためDICも良くなった、これは医学的にはあり得ない。通常、脳静脈洞血栓症の抗凝固療法は、少なくとも2週間は要するが、本件は半日の治療でほぼ良くなっていて、1日半で治療を切り上げている。外からバランスを整える薬を投与することによって、状態は何とか安定化させることはできるが、1日半で治療をやめて再燃しないはずはない(C16、35、37、38)。
〔2〕CT画像との整合への反論
BのCT画像に見られる大脳鎌近傍の高吸収域は、硬膜下血腫とくも膜下出血の混在したものと見るべきであるとし、〔1〕通常は確認され難い前下方の大脳鎌が明確に確認された場合、大脳鎌のように見えるが、大脳鎌を見ているものではないとして偽性大脳鎌徴候(フォールスファルクスサイン)といわれており、大脳半球間裂の急性硬膜下血腫である可能性が高いということで、これを疑う端緒になるところ、Bの場合にもこの所見がある、〔2〕出血は、漏れ出て固まって液体成分が抜けて初めて、血液はCTで白く写って確認できることになるから、血管の中の成分が怒張して止まっている、うっ滞しているから白く写るということは、CTの原理上あり得ない、〔3〕静脈洞の中の血栓である白くなったものは、単純CTでもデンスクロットサインとして確認することができるが、血栓は血管の中の固まりであるから、静脈洞の構造を超えて白くなるということは物理的にあり得ないところ、BのCTでは、静脈洞と想定される部位をはるかに超えて、白い高吸収域がはみ出しており、これは血栓ではあり得ない所見であり、デンスクロットサインではないと判断され、くも膜下出血と硬膜下血腫が混在したものと医学的には判断される(C5~14)。
〔3〕Bの症状との整合への反論
小児における1次性(内因性)の脳静脈洞血栓症は、ほぼ全例が亜急性に進行し、その経過は、しばしば数日間を掛けて完成する。これまで元気だった子が、急激に発症して心肺停止に陥って救急車で運ばれてしまうという経過をとることはこれまで一例も報告されていない。Bの臨床経過は、これと合わない(C26、27)。
4 各医師の見解を踏まえての検討(所論の指摘する内因性の原因である可能性の検討)
(1)検討方法
そこで、E証言及びF証言並びにこれに反論するC証言を踏まえて、Bの症状の原因が、外力によるものではない可能性について検討する。
原判決は、Bの症状が外傷によるとした根拠として、SBS理論に立脚したC証言に大きく依拠しているものと思われる。SBS理論(単純化していえば、SBSに特徴的とされる、〔1〕硬膜下血腫、〔2〕脳浮腫、〔3〕眼底出血の3徴候があった場合、虐待による揺さぶり行為があったと認め得るという考え方)に対しては、弁護人が控訴趣意書で指摘するように、それがどの程度信頼できるのかといった疑問や、信頼できるとしてその使い方についての議論も存在するやにうかがわれるが、本件の審理においては、SBS理論自体の適否は争点とはなっておらず、これについて直接的に検討することはしていないから、ひとまずSBS理論を前提にしている。
そうすると、Bの症状が外力によると推認してよいかは、SBS理論で外力を推認させる3徴候が合理的な疑いなく認められるのかという問題となる。原判決に即していえば、Bの所見として、急性硬膜下血腫(及び多発性のくも膜下出血)、びまん性脳損傷に続発した脳浮腫、両目の広範囲にわたる多発多層性網膜出血が認められるのかを検討することになる。
もっとも、所論は、Bの症状の原因が外力でなかった可能性を具体的に指摘している。すなわち、内因性の脳静脈洞血栓症とDICである可能性を論じているのである。Bの症状が外力によるものか、内因性のものかは、両者が競合する場合があり得るとはいえ、本件では基本的には矛盾する構造となっており、検察官も両者の競合であるとの主張はしていない。
したがって、当裁判所としては、各医師の前記見解に照らし、内因性である可能性を指摘するE、Fの各証言を、これを批判するC証言と対比させて検討し、内因性の可能性について判断することとする。
(2)血液データ及びその後の治療経過との整合性(〔1〕、〔4〕)について
ア E医師は、脳静脈洞血栓症とは、頭部の太い血管に血の固まりができる病気であり、主に太い静脈のところに血の固まりができることによって、脳に戻ってくる静脈の血液がうっ滞し、脳にも損傷が起こってくるという病気であり(E2-4)、前述のとおり、Bの搬送直後の血液検査で血液凝固系の数値が異常値を示していることが、脳静脈洞血栓症を発症していることを表しており、血液凝固異常に対するBの治療経過も、内因性の脳静脈洞血栓症を発症していたことと矛盾しない旨証言し、F医師も同旨の証言をする。
E医師及びF医師は、その学識、経歴や豊富な実績に照らすと、脳神経外科学に関する専門的知見を述べる証人として、共に十分な資質を備えている。E医師は、小児の脳出血に関して、血液凝固異常と硬膜下血腫について、学会で発表し、小児脳神経外科の教科書で脳静脈洞血栓症のパートを担当し、小児を含む脳静脈洞血栓症の治療経験を有している。F医師も、脳静脈洞血栓症の治療経験は成人に限られるものの、高度救命救急センターの頭部外傷治療のチーフを務め、現在は脳神経外科と兼務して小児医療センターでも勤務しており、小児を含む豊富な重症頭部外傷の治療経験を有している。両名ともに、検察側の証人として法廷で証言した経験も有し、偏りがあることはうかがわれず、この分野における専門的知見を述べる証人として、一般的に信用性に欠けるところはないと認められる(E2-1~3、6、F1、2)。そして、その内容は、専門家としての合理的な推論によって導かれたものと評価できる。
そうすると、E医師及びF医師の各証言によれば、搬送直後の血液検査の結果で、血液凝固系の数値が大幅な異常値を示しているのは、脳静脈洞血栓症を発症しており、血液凝固因子が大量に消費されたためではないかという疑いが生じる。
イ これに対し、検察官は、次のとおり反論する。小児の脳静脈洞血栓症の患者に対して投薬治療や抗凝固療法は、基本的にはC医師のような小児科医が主治医として行うもので、脳神経外科医が主治医となって行うことはほぼない(C34)。E医師は、1例あるという小児の脳静脈洞血栓症の臨床経験においても、投薬治療を主治医として決めたものではなく(E3-36)、血栓が全部溶けなくても回復に向かうことがある旨の証言の根拠も、足の深部静脈血栓症の治療経験からの推論にすぎない(E3-37~39)。また、乳児の方が凝固線溶系のバランスが崩れやすく(E3-20)、成人の臨床経験がそのまま活かせないところ、F医師には小児の脳静脈洞血栓症の治療経験がない(F20)。小児の血栓凝固止血に関して、C医師は、臨床的に少なくとも12例のDICの治療に関わっているから(C87)、主体的な立場での臨床経験に基づく証言ができるのは、3名の医師のうち、C医師のみであり、C証言は極めて信用性が高いのに対し、E医師及びF医師の各証言はいずれも信用できないと主張する。
しかし、医学的知見について、臨床経験数は供述の信用性判断の一資料とはなっても、それが全てではない。しかも、小児の脳静脈洞血栓症の治療経験は、C医師も新生児2例、14歳の子1例の3例であり(C33)、新生児1例のE医師と比べても、いずれも多いとはいえず、経験からの知見に極端な差が出るとも考え難い(E2-28)。E医師は、その1例について、主治医として決定したものでなくとも、上司の手足のように動いて治療に携わっていたというのであり、投薬治療の臨床経験としては遜色のないものといえる(E3-36)。逆に、F医師は、成人の脳静脈洞血栓症の治療経験は十数例と豊富にあるのであり(F20)、小児の特質を踏まえた上で、成人の臨床経験から推論することも、医学的知見として尊重できるものであるが、小児科医であるC医師にはそのような知見はない。また、小児の血栓凝固止血の投薬治療に関して、E医師も、外傷、白血病、血友病等でDICになっている小児の患者をチームとして診ていた経験は多数あり、病院によっては小児科ではなく、脳外科と救急医療科で投薬方針を決めることもあるというのであるから(E3-36、37)、臨床的に少なくとも12例というC医師のDIC治療経験が、他の医師の意見を排斥するほど極めて信用性が高いものであると断定することはできない。
ウ また、C医師は、1日半の抗凝固療法で血栓が全て完全に溶けてなくなってしまった、少なくとも、E医師らがそのような見解であるという前提で反論しているが、同医師らも血栓が「全て」「完全に」溶けたなどとは証言しておらず、前提に誤りがある。E医師も、一般的には、時間がかかって血栓がなかなか流れないケースが多いとした上で、血栓が完全に溶けてなくならなくとも、一部が溶ければ血液は流れ、血液凝固系の数値もかなり回復に向かうと述べているのであり、このこと自体は合理性があるものと思料される。E医師が、C証言(脳静脈洞血栓症の血栓が溶けたものであるとすると、Bの治療経過は医学的にあり得ないと断言する。)に疑問を呈し、その可能性は十分あると述べているのも(E3-13、14)、首肯できる。
エ C医師は、小児重症頭部外傷事例でDICの診断を満たす凝固系の異常はかなりの確率で出る、Bのように、わずか6時間の治療で正常化し、ヘパリン投与を含む治療を翌日にやめられるようなDICはなく、DICの治療は2週間以上、もしくは1か月以上かかるものである、頭部外傷に続発した凝固異常は、純粋な意味でのDICとは異なり、ほとんどの患者が24時間以内に治る、これは国際止血学会でもいわれているとおりである、つまり、Bは、純粋なDICではなく、ACOTS(アコッツ。激烈なDICのように見えるが、DICではなく、コントールされてしまう病態で、数日で治る。)である旨証言している(C27~29)。検察官は、この証言が自己の臨床経験を基盤として、さらに、明確な医学的根拠を示して行われたものであって、信用性は極めて高いと主張する。
しかし、E医師も、小児重症頭部外傷事例でDICの診断を満たす凝固系の異常が出る場合があることを前提とした上で、頭部外傷では、PT-INR値が異常値を示しても、通常2を超えるということはないのに対し、Bは測定不能になるぐらい振り切れている点が、外傷と整合しないと指摘しているのであり(E2-16)、C証言は、この頭部外傷の場合における異常値と本件におけるそれとの顕著な違いについて、的確な反論ができているとは評価できない。
他方、E医師は、小児重症頭部外傷事例では、DIC診断レベルの凝固異常は頻発する、ということを示すためにC医師が引用した論文(C医師の証人尋問調書速記録末尾添付の別紙1の22枚目、以下「スライド22枚目」のように表記する。)を確認したところ、最も重症な9例についての表を見る限り、フィブリノゲンが50を下回っている症例というのはなく、Bの症例はかなり特異な経過だったと思われる(E3-14、15)、また、大人の重症頭部外傷のDICとの関係を示した別の論文から引用した表によれば、大人の最重症の方であっても、やはりフィブリノゲンが50を下回ることはないのは上記小児の場合と共通しており、PT-INR値は、大人の場合ではあるが、やはり1.4すら超えない、超えたとしても2とか、正常よりも若干平均値として上がってきているという程度であり、外傷でPT-INR値がBの場合のように極端に振り切れる、高度の値を示すというのは、常識ではあり得ないことであると供述する(E3-14、15、速記録末尾添付の別紙14)。このように、E証言は、Bの血液データが、重症頭部外傷事例と比較して顕著な特異性を有することを、根拠となる医学論文の客観的なデータを示して説明するもので、合理的かつ説得的な内容であり、信用性が高いと認めることができる。
C医師は、一般的に、DICの治療は、1日半で終わらせることはとてもできないことを示すために、DICの治療に長期間を要した3つのグラフを挙げているが(スライド21枚目)、そこで例示している基礎疾患は、繰り返す急性ステント血栓症を来した一例、敗血症、平滑筋肉腫(がん)という重篤な基礎疾患であって(C57)、E医師やF医師が指摘した凝固異常などの疾患とは異なる。C医師の挙げた例示は、F医師が、DICで凝固系の数値が容易に回復しない基礎疾患として考えられるものとして除外した例である、末期のがん、白血病、重症感染症で敗血症になっているような場合にまさに該当するものといえ、Bの治療経過がDICの治療経過と整合しないことを根拠付けるものとはいえない。脳静脈洞血栓症は、ヘパリンという血栓を溶かす薬である抗凝固剤を使うことによって、悪循環のもとである脳静脈洞血栓症の固まりが溶けて、さっと流れて、1日、2日で回復に向かうこともあり得るというF証言(F16、17)及びこれと同旨のE証言を、C証言によって排斥することは困難である。
オ 以上によれば、Bが脳静脈洞血栓症であったことについて、Bの血液データが整合し、その後の治療経過も矛盾するものではないというE医師及びF医師の証言は合理性を有し、検察官の指摘する点を踏まえても、その信用性は揺るがない。そして、Bの血液データの点は、外傷性であるとした場合は、顕著な特異性を有している、すなわち、外傷による場合は、通常考え難い数値であることも示していると評価できる。
(3)CT画像との整合性(〔2〕)について
ア E医師は、前述のとおり、BのCT画像で、上矢状静脈洞に白く三角形に写っているのは、脳静脈洞血栓症によって形成された血栓が写っている可能性がある旨証言し、F医師も、Bの場合にも、脳静脈洞血栓症の大切な所見である、大脳鎌や小脳テントそのものが肥厚し、そこに血液がうっ滞する、もしくは血栓が生じるという所見がある旨証言する。
E医師及びF医師は、ともに脳神経外科医であり、常日頃、臨床等で脳のCT画像の読影を行っている専門家であるから、その両医師が、BのCT画像上の特徴を指摘している以上、その証言は、特段の事情がない限り信用性を認めて差し支えないものであり、CT画像の所見からも、脳静脈洞血栓症を発症していたのではないかとの合理的な疑いが生じる。
イ もっとも、F証言については、検察官が指摘するとおり、脳静脈洞血栓症であるか否かの確定診断のためには、通常、造影CTかMRIを撮る必要があるとされており、F医師もこれを認めているところ(E2-12、13、28、C11、12、F29)、同じ脳神経外科医であるE医師が、脳静脈洞血栓症によって形成された血栓が写っている可能性があると自身が指摘している箇所について、硬膜下血腫と見ることも可能である旨控えめな証言をしているのに対し(E2-31)、F医師は、大脳鎌と小脳テントが写っているのを急性硬膜下血腫と誤認している(F17、18)、単純CTを見ただけでも大脳鎌が肥厚して白く写っているのか、出血があるのかというのは分かるという趣旨(F26、27)の証言をしている。しかし、F証言のこの点は、いささか断定的にすぎるきらいがある。加えて、当審では、BのCT画像の大脳半球間裂付近の高吸収域が、急性硬膜下血腫であるのか大脳鎌の血栓であるのかは、当初より重要な争点の一つとされていたところ、F医師は、鑑定書(当審検20[当審弁2として請求されていたもの、作成年月日平成30年3月22日]においては、同じCT画像の所見として、「単純に急性硬膜下血腫の存在も考えられる」としていたから、本件の核心部分につき変遷があるといわざるを得ない。以上の点からすれば、F証言は、CT画像所見のみを根拠に、急性硬膜下血腫とみるのは誤りである旨断定的に述べる点には疑問を差し挟む余地があるが、だからといって、F証言全体が信用できなくなるとも考え難い。
一方、E証言について、検察官は、E医師の脳静脈洞血栓症の臨床経験、特に小児についてのそれが少なく、臨床上、CT画像をほとんど見ていないことを根拠に信用性を否定するが、前述のとおり、E医師は、小児の脳出血に関して学会で発表し、小児脳神経外科の教科書で脳静脈洞血栓症のパートを執筆してもいるのであり、これらを行うに際しては、自身の臨床経験以外に、過去の文献や他の臨床例に基づくCT画像等も収集して分析、検討しているものと合理的に推察できる。当該症例の臨床経験数のみを根拠に、CT画像の読影結果の信用性が否定されるものではない。
ウ 検察官は、E医師が、BのCT画像の白色の三角形が、脳静脈洞血栓症に特徴的な所見とされる、デンスクロットサインか否かの比較対象に、大人の脳静脈洞血栓症のCTを用いている(E2-7、8、33)のも問題であると指摘するが、小児との違いを踏まえる必要はあるとしても、成人の所見を参考にすること自体を論難できる理由はない。
エ 検察官は、BのCT画像上、解剖学的に考えられる脳静脈洞の形(正三角形に近い形)を大きめにとっても、なおその外側に白い高吸収域が写っているという点につき、E医師は、乳児の静脈洞は細長い煙突形の三角形をしていると聞いたことがある(E3-5、別紙4)、大脳鎌の中の静脈叢と静脈洞が引っ掛けて写っている可能性がある(E3-5)、CT画像のスライスする部位によって大脳鎌の血栓まで一緒に写り込む(E3-28)などと証言するが、いずれにしても、小児の脳静脈洞血栓症の臨床経験に基づく証言でないばかりか、前記細長い煙突形の三角形の外側(右の外側など)にも白い高吸収域が写っているのは、出血(硬膜下血腫とくも膜下出血の混在)以外に説明しようがないとし(C11、スライド9枚目)、BのCT画像を根拠に脳静脈洞血栓症とする点は、根拠としては薄弱で、むしろ硬膜下血腫とくも膜下出血の混在があったことを表していると主張する。
検察官のこの点の主張は、以下のようなC証言に依拠しているものと思われるので、その点についても検討を加えておく。すなわち、C医師は、CT画像上、血管内を流れている血液は、たとえうっ滞していたとしても、決して白くは写らないことを前提に、白く写るのは、血液が漏れ出て固まって液体成分が抜けた場合、すなわち出血と、血管内で血栓を作って血の固まりになり液体成分が抜けた場合、つまり血栓であるという理解の下、静脈のうっ滞、怒張によって、血管の中の成分がとどまっているから白く写るという弁護側証人の証言は、CTの原理上あり得ないと否定している(C9、10)。
この点、画像診断における基本的な医学文献には、「高吸収域をみることがある」のは「血管内の塞栓子あるいは停滞した血液が描出されていると考えられ」るという記述や、「出血しなくても、組織内や血管内で血球の密度が亢進すれば、高吸収になる。組織内や血管内のうっ血、血栓などは高吸収である。」という記述がある(C43~45、別紙2、3)。そのメカニズムは、E医師の説明内容と符合するものであり(E3-1)、E証言及びF証言は、そのような見方もあり得るという意味において、医学文献上の根拠があるといってよい。これに対し、前記のとおり、画像診断学の常識であるとまで言い切って、静脈のうっ滞、怒張が白く写ることはあり得ないと否定するC証言(C43)は、医学文献の記載と整合せず、CT画像の読影について、正確な専門的知見を有しているのか、本件に即していえば、白く写っている部分が、硬膜下血腫等の出血であるのか、それとも、それ以外の可能性があるのかという鑑別診断を正確に行うことができるのかにつき、疑問を禁じ得ない。C証言は、その断定的な言いぶりに照らしても、自己の拠って立つ見解を当然視し、一面的な見方をしているのではないかを慎重に検討する必要がある。
そして、検察官は、血栓は血管の中の固まりであるから、静脈洞の三角形の構造を超えて白く写るということは物理的にあり得ない、BのCT画像上、三角形の右上側などにも白い高CT値がはみ出しているのは、血栓ではあり得ない所見であるから、脳静脈洞血栓症に特徴的とされるデンスクロットサインではなく、くも膜下出血と硬膜下血腫が混在したものと判断されるものであるとのC証言(C10、11)に依拠して、この所見を脳静脈洞血栓症であったとは認められないことを示すものとして指摘する。
しかし、E医師は、分娩時の外傷により硬膜下血腫を生じて血塊ができている生後2日目の乳児のケースで開頭手術を行った経験から、直接、大脳鎌を目視した経験上、静脈の血栓やうっ血によって、二次的に大脳鎌が厚くなるというような状況が生じると思われること、上記症例は、小脳テント内の静脈叢というところから出血していた事例であったことを証言している。また、医学文献上、硬膜と硬膜の間に、静脈の静脈叢とよばれる部分が形成されていることが解剖学的知見から判明していること、静脈洞血栓症を来した成人女性の症例報告で、大脳鎌のところに静脈洞様に広がっている部分が存在するという報告があり、大脳鎌の中にもこのような静脈洞様の構造があるというのは、比較的珍しいものではないとの記述があることを証言している(E3-1ないし5、別紙1ないし3)。E証言は、自身の臨床経験に基づいて、上記開頭手術の際に撮影された写真を示しながら該当箇所を説明するという具体的な供述で、その内容に沿った医学文献上の症例報告という根拠もあるなど、説得力のある内容であって、信用することができる。
そうすると、検察官が脳静脈洞血栓症であったとはいえないことの根拠とする、静脈洞の三角形の構造を超えて白く写っている部分については、E医師が説明するように、大脳鎌の中の静脈叢の部分が一部写っている可能性や、硬膜の中の静脈叢が一部写っている可能性なども十分考えられるから、これらの白い部分があったからといって、Bに脳静脈洞血栓症があったことが否定されるものではない。
オ 以上によれば、BのCT画像について、脳神経外科医の専門家2人が一致して、脳静脈洞血栓症に特徴的な所見と見ることができる旨述べていることには、相応の根拠が認められ、誤った読影であるとして排斥することはできない。もっとも、造影CT等の必要な検査を実施していない以上、脳静脈洞血栓症の所見であると認められるとの確定診断は元々できないものであり、逆に、E医師自身も、この所見を硬膜下血腫と見ることも否定はしていない(E3-6)。
要するに、CT画像の読影のみからは、硬膜下血腫とくも膜下出血の混在したものであるとも、脳静脈洞血栓症であるとも断定できないのであり、少なくとも、BのCT画像は、脳静脈洞血栓症に特徴的な所見と矛盾するものではないことは明らかといえる。
そして、このことは、BのCT画像からみて、Bに硬膜下血腫があると断定してSBS理論を適用することにつき、合理的な疑問を投げかけるものでもある。
(4)Bの症状との整合性(〔3〕)について
E医師は、前述のとおり、呼吸障害、意識障害といった搬送当日のBの症状は、脳静脈洞血栓症の症状と矛盾はなく、比較的早期に病態が進行することもあり得ると証言し、F医師も同旨の証言をしており、医学的知見や経験に基づくもので信用性が認められる。
そうすると、Bは、内因性の脳静脈洞血栓症を発症したことにより、急激に症状が悪化するという本件における展開をたどったのではないかという疑いが生じる。
これに対し、検察官は、小児における内因性の脳静脈洞血栓症は、ほぼ全例が亜急性に進行し、病態が完成するまでには通常は数日かかるという前述のC証言は、臨床経験や医学文献に基づく客観性のあるもので信用できるとし、Bは、あまりに急激な経過をたどっており、上記発症経過と整合しないと主張する。
この点、E医師が、血栓が雪だるま式に膨れてくるため、比較的早期に病態が進行することもあり得るとして想定しているのも、1日ないし1日以内(E2-11)とか、半日ぐらい(E3-12)の時間をかけて、徐々に血栓ができてきた可能性をいうものであり、これまで元気だった子が、ちょっとの隙に急激に発症して、もう心肺停止に陥るというようなC証言(C26)にあるほどの急激さを前提としてはいない。そして、F医師も、臨床経験上、成人で、1日前まで、あるいは、当日朝まで何もなかったという人が、突然、脳静脈洞血栓症で搬送され、くも膜下出血や脳出血を生じているようなケースを見ていると証言しており(F24、25)、E医師がいうのと同程度の急激な経過で発症した実臨床上の裏付けがある。そうすると、F医師の見解にもあるとおり(F25)、成人で見られるのであれば、よりか弱い乳児の場合に起こり得ないとする理由はない。
この点、C医師は、Bのような急激な発症経過をたどった例は、「一例も報告がない」(C26、スライド19)とするが、C医師が世界中のあらゆる文献を精査したのかは疑問であり、その証言には自ずと限界があり(イギリスで証言停止になった医師が執筆したものであるとして、検察官が証明力を争う論文ではあるが、脳静脈洞血栓症の「乳児の少なくとも10%は無症候性であり」(当審弁6、26頁)という記述があるほか、「皮質静脈および静脈洞血栓症。公立の公園で倒れ、虚脱状態となった4週齢の乳児。」との説明を付して写真付きで症例が報告されてはいる(同29頁)。)、前記成人における事例の存在に照らしても、C医師がそのような報告例に接したことがないとしても、起こり得ない発症経過であると断定する点は必ずしも信用できない。
なお、C医師は、急激に脳静脈洞システム全部に血栓ができて、全体的に広範に全て詰まってしまうというのは極めて考えづらいと供述するが(C15、16、スライド12)、E医師も、脳静脈洞システム全部が全て詰まってしまうような状況を前提としてはいないし、部分的に詰まるだけでも十分説明は可能である旨供述しているところである(E3-12、13)。
以上によれば、本件当日に見られたBの症状も、脳静脈洞血栓症と矛盾しないものであり、比較的短時間で急激な展開をたどったその発生機序も現実にあり得るものといってよい。
(5)脳静脈洞血栓症、DICにより、くも膜下出血が生じた可能性について(〔5〕)
Bに生じた、くも膜下出血の発生機序について、E医師は、動脈から脳に供給された血液は、静脈側に流れていくが、その出口が血栓で塞がれた状態になっているため、動脈圧がどんどん上がっていき、最後にそこのところの非常に弱い血管が破綻して、出血という結果になったと考えられる旨証言する(E2-19)。その説明は合理的であり、C医師も、同様の機序で脳静脈洞血栓症からくも膜下出血を起こすことがあり得ることは認めている(C16)。
また、Bのくも膜下出血が、非常に広範囲に生じていること(E2-20等)についても、C医師も前提にしており争いはないが、それをどう見るかという評価については、E医師及びF医師が、頭部外傷によるくも膜下出血は、通常局所に発生することが多く、このような広範囲のものは臨床上あまり見たことがないとして、内因性のものと考えるのが妥当であるという趣旨の証言をするのに対し(E2-35、36、3-12、F13、14)、C医師は、あまりに全体に広がりすぎており、至る所の血管が完全に詰まっていることを意味するから、脳静脈洞血栓症のみに根拠を求めるのは無理があると証言して対立している(C17)。このこと自体から、脳静脈洞血栓症を基礎づける決め手とすることはできないが、少なくとも、Bのくも膜下出血は、内因性の脳静脈洞血栓症と矛盾するものではない。
(6)小児の脳静脈洞血栓症は非常にまれであり、凝固系異常等の考えられる原因疾患も否定できるとの検察官の主張について
ア 検察官は、脳静脈洞血栓症は、カナダの統計では10万人に対して0.67人の発症率とされているなど、極めてまれな症状であり、各医師の臨床経験数からも分かると指摘する(C19、E2-5、6など)。
この点、弁護人は、C医師が指摘したデータは2008年のものであり、その時点でも、小児血栓症の認識が高まったことにより、過去5年間で倍増したとされており(C67頁)、それから10年以上が経過しているのであるから、C医師が指摘した論文、数字に依拠して、脳静脈洞血栓症が極めてまれだと結論付けることはできないと主張するが、このような変化を踏まえても、小児の脳静脈洞血栓症がまれな疾患であることに変わりはない。もっとも、どれだけ確率的にまれな疾患であっても、相応の根拠を持って脳静脈洞血栓症である可能性が指摘されていれば、出現の確率が極めて低いことのみを理由に、脳静脈洞血栓症ではないと結論付けることが許されないことは疑いない。本件の場合は、これまで検討してきたように、血液データの数値と整合し、CT画像等とも矛盾しないなど、相応に裏付けとなる内容を伴っている場合であるから、小児の脳静脈洞血栓症が確率が低いまれな疾患であることをもって、発症を否定する理由とする検察官の主張は採用できない。
イ また、検察官は、E医師が、Bの脳静脈洞血栓症が発症した原因の1つとして示した、内因性の血液凝固異常について、すなわち、血液を固まりにくくする因子である、プロテインS、プロテインC、アンチトロンビン〈3〉、ファクターVライデン等の異常があった可能性があり(E2-5、11)、例えば、プロテインSの部分基質(ヘテロ体)があるなど凝固因子が若干低く、ちょっとミルクを飲まないなどの理由で軽い脱水を起こすなどしてストレスがかかり、血栓が生じた可能性がある(E2-11、43、44)と指摘したのに対し、C証言に依拠して、そのような原因疾患は否定できると主張する。
この点、C医師は詳細に反論しているが、その細部について検討するには及ばない。そもそも、E医師もF医師も、Bの脳静脈洞血栓症の原因はよく分からない、不明であるとの前提に立っているのであり(E2-43)、弁護人の所論も当然その前提である。E医師が示した上記疾患は、あくまでも原因となる基礎疾患として考え得るものを1つの可能性として提示したにすぎず、プロテインS、プロテインCなどの欠損症がBの基礎疾患であったと、限定した主張をしているわけではない。F証言によれば、小児の脳静脈洞血栓症の13%から18%は原因不明とされており(F21)、臨床経験上も、E医師の小児例は原因不明で、成人にも原因不明のものがあったし、F医師も過去3年間に4人の成人例があったが、いずれも原因不明であったと述べている(E2-6、F20)。これらからすると、Bの場合も原因不明であったとしても、特段不合理とはいえず、原因が特定できていないことは、脳静脈洞血栓症の可能性を否定することにはならない。
(7)小括
以上によれば、Bの症状が外力によるものではなく、内因性の脳静脈洞血栓症とDICによるものである合理的な可能性が認められる。とりわけ、Bの血液データは、どちらかといえば、Bの症状が外力によるものであるとすると矛盾する方向にあることも否定できない。
5 原判決の推認についての医学的な見地からの検討
以上の検討により、既に、原判決には事実誤認の疑いがあることになるが、ここでは、念のため、原判決が、積極的に外力によるものであると認めた根拠について、各医師の見解を踏まえて検討しておく。なお、事柄の性質上、前項4で検討した内容と重複することがあり得る。
(1)硬膜下血腫が生じていたと断定できない
原審では、硬膜下血腫があったことに争いはないとされていたが、当審では、弁護人は、その前提も誤っているとして、硬膜下血腫の存在を争い、その根拠として、〔1〕E医師及びF医師が、硬膜下血腫の存在に否定的な証言をしている、〔2〕CT撮影後のカルテにも硬膜下血腫の記載はない、〔3〕CT画像所見から、うっ血や血栓でないとはいえない、〔4〕大脳鎌はCT画像で確認できないとのC医師の意見は誤りである、〔5〕脳表と硬膜の癒着は硬膜下血腫だと断定する根拠にならない、という点を挙げている。
この点は、SBS理論では、外力を推認する重要な徴候の一つであるとされるので、検察官の反論も踏まえつつ、検討する。
ア 〔1〕及び〔3〕の点は、既に検討したとおり、CT画像のみから、急性硬膜下血腫とみるのは誤りである旨断言するF証言は採用できないが、E証言から、少なくとも、CT画像だけで硬膜下血腫があったと断言することは難しく、それをうっ血ないし血栓であるとするのが、明らかに誤った読影であるとして排斥することはできない。
イ 〔2〕の点は、前記2オのとおり、CTを撮影した直後のカルテには、2名の小児科医により、「脳浮腫とくも膜下出血を疑う」「脳浮腫、くも膜下出血、左側脳室出血あり」とそれなりに詳細な記載がされているが、硬膜下血腫の記載はない。このようなカルテの記載からすると、少なくとも、明らかに硬膜下血腫と診断できるような所見はなく、上記2名の医師は、当時、硬膜下血腫ないしその疑いがあるとは考えていなかったと認められる。
ウ 〔4〕の点は、前記3(2)〔2〕のC証言要旨〔1〕にある、大脳鎌と思って見ているものは大脳半球間裂の急性硬膜下血腫である可能性が高いという偽性大脳鎌徴候(フォールスファルクスサイン)に関連する。E証言によれば、C証言が依拠する論文(スライド7枚目、「子ども虐待の画像診断」C医師監訳)の原典(1980年代の放射線科の医学論文「ラジオロジー」に掲載されていたオズボーンの論文)を全文読んで確認したところ、当時のCTは画質も非常に悪く、一見すると硬膜下血腫やくも膜下出血に見えるものは、実は正常構造の静脈洞や大脳鎌であったりするという趣旨の論文であり、そのような趣旨でフォールス、すなわち、本当は何も所見がないという意味で、フォールスファルクスサインというふうになったという記載があったとのことである(E3-9、10)。すなわち、C証言は、原典とは全く逆の意味で説明したことになる。C医師が依拠した論文自体(C医師自身が監訳している。)が、原典の趣旨を正反対の意味に用いたことが疑われる不誠実な引用がなされているものといわざるを得ない。Bの所見も、この偽性大脳鎌徴候(フォールスファルクスサイン)に当たることを理由に、大脳半球間裂の急性硬膜下血腫であるとするC医師の見解は、その依拠した論文自体の信用性が乏しく、採用できない。
エ 〔5〕の点は、Bの解剖所見(原審甲57)では、要旨、Bの硬膜と脳表の癒着は、脳表全体に広範囲に広がっていたから、硬膜下血腫は脳全体に広がっていたと考えられた、仮に、Bがくも膜下出血のみを起こし、硬膜下出血がなかったのであれば、出血した血液は、くも膜に隔てられているため、通常は、硬膜に癒着することはない(例外的に髄膜炎の場合が考えられるが、Bにはその症状はなく否定できる。)として、硬膜下血腫が存在する根拠として、脳表と硬膜が癒着していたことが挙げられ、D医師も同旨の証言をしていた(原審第3回公判D医師の証人尋問調書2頁以下)。
しかし、F医師は、開頭手術の臨床経験上、くも膜下出血が起こると、人体は血腫を吸収するために、広い意味でも炎症性の反応が起こるから、脳の表面と硬膜は癒着するものである、急性硬膜下血腫以外で開頭手術をすると、脳梗塞であろうが脳腫瘍であろうが、癒着をするということは決してまれではないと証言し(F12、13)、E医師も、硬膜下血腫があるから脳と硬膜が癒着するというわけではなく、脳が腫れ上がっている患者でも癒着するということはしばしば経験すると証言する(E2-22)。生きた人間の頭を開けることができる脳神経外科医だけが知る知見として、2名の脳神経外科医が一致して述べる見解である上、F医師が、Bのように、広範なくも膜下出血があった状態で、しかも3か月後、脳が壊死して相当なダメージが加わり、いろんな反応が起こってしまっている状況下で、硬膜と脳表が癒着していない方がおかしいと述べるのは十分に説得的である。
よって、解剖時に、脳表と硬膜が癒着していたことは、必ずしも、発症時に硬膜下血腫があったということのみを指すとは限らないと判断される。
オ さらに、解剖所見では、くも膜や硬膜は厚ぼったくなっており、血球を取り込んだ貪食細胞が多数認められた、出血した血液は貪食細胞に取り込まれて吸収されるので、くも膜下、硬膜下に出血があったことを意味し、硬膜下血腫とくも膜下出血がいずれもあったことが判明した、とされている。
この点、F医師は、解剖所見が、解剖時に(貪食細胞ではなく)血腫が存在したと指摘するものとの前提で反論を加えているため、前提において誤りがあることは検察官指摘のとおりである。しかし、F証言の要旨は、いずれにせよ、解剖時の脳表、硬膜の状態から、その数か月前の硬膜下血腫の存在を確認することはできないという点にあると解されるのであり、Bの場合、搬送後、死亡に至るまで3か月半という長期間が経過しており、解剖所見上も、脳が軟化しており、脳細胞が壊死して長期間経過していることを意味するとされている。そして、C医師自身も、原審において、くも膜下出血がくも膜を穿破して硬膜に入り込むことがあり、それが硬膜下腔にたまれば硬膜下血腫として認識される旨証言しているように(原審第3回公判C医師の証人尋問調書4頁、以下「原審C頁数」と略す。)、脳に重傷を負って壊死した後、長期間が経過している本件のような場合に、死亡時ないし解剖時の病態は、発症時の病態とは異なるものに変化してしまっている可能性は否定できない。硬膜が血球を取り込んだ貪食細胞のために厚ぼったくなっているという前記解剖所見は、発症時に硬膜下血腫が存在していたことをうかがわせるものといえなくはないが、発症時に硬膜下血腫は存在していなかったのに、その後死亡に至るまでの時間の経過の中で、そのように変化した可能性を排斥することはできない。
カ 以上に対し、検察官は、硬膜下血腫の存在を推認させる事実について、カルテの記載上、Iセンターの医師は、Bにつき、くも膜下出血と診断していたが、経験のある第三者による判定も参考にするため、Mセンター集中治療科のN医師に意見を求めたところ、N医師は、BのCT画像から、大脳鎌周辺(大脳半球間裂と同義)の硬膜下血腫があると確認したこと、原審証人のD医師も、CT画像から大脳半球間裂や小脳テントに硬膜下血腫を認めていることを挙げ、硬膜下血腫の存在が否定されるとする弁護人の主張に理由はなく、C証言の信用性は何ら揺らがないとして、原判決の事実認定には何ら論理則・経験則違反はないと主張する。
しかし、この検察官の主張に対しても、基本的には、これまでC証言について検討してきた内容が同様に当てはまるのであり、N医師(小児科医)、原審のD医師(法医)の2名が、C証言と同様の見解を述べているという以上の意味は認め難い。BのCT画像から、どのような所見が認められ、どのような病態と判断されるかは、本来的には、画像の読影技術、画像診断の知識・経験に基づくものと考えられ、N医師が意見を求められたという経緯を踏まえても、Iセンターの医師らの当初診断と、児童虐待に詳しいとされている小児科医のN医師の診断とで、後者の方が、一般的により画像読影に長けていて、その見解の方が信用できるとまではいえない。
以上によれば、原審が、揺さぶりによる外力が原因であると判断したことの重要な前提となっていた、Bに硬膜下血腫が存在していたという点については、少なくとも、これがあったと断定することはできない。たしかに、硬膜下血腫とみる余地はあるものの、他方で、その所見をうっ血ないし血栓とみることにも合理的な根拠があり、カルテ上、CT画像を踏まえた当初診断では、硬膜下血腫とはされていなかったことなど、これを否定する方向の事情も認められるのである。SBS理論によれば、硬膜下血腫が存在することはほぼ必須であると考えられるところ、複数の医師がBについて硬膜下血腫の存在を認めていない、あるいは、くも膜下出血と診断している状況がある以上、SBS理論を適用すること自体を差し控えるべきであったと考えられるのである。
なお、検察官は、仮に硬膜下血腫が生じていたと仮定した場合、脳静脈洞血栓症によっては、硬膜下血腫は生じないとも主張するが、これは、あくまで仮定の議論である。既に、Bに硬膜下血腫が生じていなかった可能性を排斥できない以上、この点について検討する意味はない。
(2)網膜出血、胞状網膜剥離も、脳静脈洞血栓症、DICが原因と考えて矛盾しない(〔7〕)
ア DICは、全身の血管内で血液凝固反応が無秩序に起こり、血液内に微少な血栓が生じる症状のことであるが(原審甲55)、Bに生じていたDICと網膜出血の関係について、E医師は、要旨、BのDICは重篤であったので、それが原因で網膜出血、胞状網膜剥離が引き起こされたと考えて、その出血の量とも矛盾はない、その機序としては、DICで血が止まりにくいということで、網膜の弱い血管で出血が起こると考えられ、DICから重度の網膜出血が起こるという実際の症例報告もあると証言する(E2-23、3-16、17)。
E医師の説明する網膜出血に至る機序に、明白に不合理な点等は見当たらない。E医師のいう、血液凝固異常がある42例のうちの3例で、重症の網膜出血を認めたという症例報告は、検察官が指摘するように、DIC以外にも、頭部外傷事案であったり、白血病の一種が基礎疾患としてあったり、敗血症を起こしていたりしており、他の要因の影響が入り込んでいる可能性があることが否定できないから、この点を重視することは差し控えるべきであるが、それでも、機序自体の説明は考慮できるものである。
イ 検察官は、C証言に依拠して、脳静脈洞血栓症に起因する網膜出血は軽微なものがほとんどであり、Bには乳頭浮腫はなく、CTでも確認できるほど極めて高度であることから、脳静脈洞血栓症に起因して網膜出血が生じたわけではない、しかも、胞状網膜剥離、袋状に剥離するというのは何らかの外力が加わらなければ生じないのであり、DICでは説明がつかないと主張する。
ウ そこで、この点に関するC証言について検討する。C医師は、要旨、〔1〕胞状網膜剥離とは網膜分離症のことであり、網膜分離症は何らかの外傷機転が働かないと起きないから、虐待による頭部外傷に極めて特異的といわれている所見であり、そういったものがあった場合には、DICではおよそ説明がつかない、〔2〕脳静脈洞血栓症では、頭蓋内圧亢進に伴って乳頭浮腫が起こり、これに伴って出てくる網膜出血は重度の出血性網膜症にはならない、しかるに、Bには乳頭浮腫は認められない(カルテに記載がない。)、〔3〕Bの網膜出血は、CTから判断して、多層性、多発性、広範であった(C29、30、47~54)としている。
エ 〔1〕については、C医師は、Bの眼を直接診察した眼科医であるL医師がカルテ等に記載していた「胞状の網膜剥離」との診断を、「網膜分離症」と置き換えているが、不正確であり、不当である。C医師は、「胞状網膜剥離」という眼科医の用語があることを知らず、文献上の根拠等に基づいて同義と解したわけでもない。ちなみに、C医師が置き換えた網膜分離症は、日本小児眼科学会が、揺さぶられっこ症候群の説明としてホームページ上に記載した文章中にも、「網膜の出血形態のひとつである出血性網膜分離は、ゆさぶりによってのみ起こる確率が非常に高い」(当審検6、17頁)とあるとおり、虐待による頭部外傷に極めて特異的とされる所見であり、このように置き換えることは、意図したものではないとしても、虐待起因の症状であるとする方向にミスリードする危険性が高い。そのような意味を含めて、この置き換えは不正確であり、不当である。また、〔2〕については、E医師は、網膜出血は、脳静脈洞血栓症からではなく、DICから生じたという見解であり、そもそも前提を異にしているから、E医師の見解に対する適切な反論とはなり得ない。そして、〔3〕について、C医師は、原審段階から、Bの網膜出血が「スケッチからは多層性の出血であったことが強く推認される」とし(原審C25)、当審でも、CTから多層性と判断しているが、C医師自身も認めているように、L医師のスケッチはラフなもので、多層にわたる出血かどうかを判断できるような資料ではない。実際にBの眼を診察したL医師は、単層性だと診断していたことがうかがわれるから、C医師の見解とは食い違っているのである(C51)。この点、C医師は、L医師が虐待の頭部外傷に関する知識と経験を十分持ち合わせていなかったため、多層性を単層性と見誤ったかのような趣旨の証言もするが、多層なのか単層なのかは、眼底検査で判断するもので、眼科的検査における読み取りに習熟し、その能力があるか否かの問題であって、虐待の頭部外傷に関する知識や経験の有無によって診断の正確さが左右されるとは考え難い。更にいえば、本件当時、虐待に詳しい医師として、同じくCTとスケッチから診断を求められた前記N医師も、眼底出血が多層性であるとの診断はしていない(原審甲52)。頭部画像検査によって眼底出血を正確に判断することは不可能であって、検眼鏡を用いた診察が不可欠であるとされているから(当審検14の647頁、「子ども虐待における眼損傷」、監訳者の1人がC医師)、検眼鏡を用いて診察した眼科医の所見の方が一般的には信用できる。C証言によって、Bの網膜出血を「多層性」だと断定することはできず、他にそのように診断するだけの根拠はないといわざるを得ない。
オ そして、DICから網膜剥離が生じうるかという点については、前記文献において(当審検14、634頁)、「外傷が疑われる眼所見」(表44-1)として、外傷であることが確定的な眼所見、通常は外傷に起因する眼所見、外傷の可能性が疑われる眼所見(特に片眼のみの場合)という3段階のうち、網膜剥離はその3番目に列挙されている。これらの所見は、様々な要因によっても生じうるものであり、何らかの内因性疾患を考慮すべき要因が何も存在しない場合に、外傷性の所見であることを強く疑う根拠となる、とされていることからすると、本件の網膜剥離も例外ではなく、外傷以外で発生する可能性がないとはいえない。
したがって、網膜出血、胞状網膜剥離も、内因性の脳静脈洞血栓症やDICが原因と考えて、矛盾しない。
(3)脳浮腫も、脳静脈洞血栓症によって生じたとして説明できる(〔8〕)
Bの脳浮腫について、E医師は、脳静脈洞血栓症であったとすると、血液が静脈側に戻ってこないため、組織も当然うっ滞して腫れてくるから、矛盾なく説明できると証言し(E2-24)、合理的な内容であり、C医師も反論していない。
(4)小括
以上により、原判決がBの症状が外力によると推認した根拠は、失われたといってよい。
すなわち、本件では、SBSに特徴的とされる、〔1〕硬膜下血腫、〔2〕脳浮腫、〔3〕眼底出血の3徴候につき、〔1〕架橋静脈の断裂により通常生じるとされる硬膜下血腫はその存在を確定できないし、〔2〕脳浮腫及び〔3〕眼底出血については、その徴候を認めるとしても、別原因を考え得ることが明らかになった(眼底出血については、多発性ではあるが、多層性であると認めるだけの証拠はない。)。
そして、本件は、一面で、SBS理論による事実認定の危うさを示してもおり、SBS理論を単純に適用すると、極めて機械的、画一的な事実認定を招き、結論として、事実を誤認するおそれを生じさせかねないものである。
6 医学的視点以外の事情からの検討
本件は、Bの突然の症状出現に端を発していることから、その発症のメカニズムの解明、換言すれば、医学的な検討なしには事案の解明はできない。しかし、医学的な解明とはいっても、どこまで解明できるかは事案によるし、ある程度承認された知見であっても、絶対ではないこと、ましてや見解につき争いがある場合には、相当程度慎重に取り扱う必要があることは、これまでの医学的検討をみても了解できることである。
そこで、客観的証拠、客観的事実とされる医学的な検討に加えて、事件が起きたとされる当時の被告人、被害者等の関係者の状況、事件現場の状況等も相応に考慮して、検討することも必要と思われる(この点は、控訴趣意書でも若干触れられている。)。
以下、そのような観点から、簡潔に検討を加える。
(1)前提事実
被告人とBの従前の関わり、本件当日の状況等について、前記第4の2で認定した事実に加えて、以下の事実が認められる(被告人の供述しかない部分は、被告人の供述を示しておくが、被告人の供述を検討もしないままに信用するということではない。)。
ア 被告人は、本件当時、毎日のように孫であるBの世話をしに行っていたが、本件当日は、午後零時3分、被告人から孫の顔を見たいとして、Aに電話をかけたところ、Aから、被告人が来てくれるなら銀行に行きたいので、娘たちを見ていてほしい旨頼まれたため、午後2時20分頃、本件マンションに赴いた。
イ 被告人は、Aが外出後、午後3時41分から56秒間、午後4時6分から2分44秒間、午後4時41分から3分7秒間の3回、同女と電話で話をしているが、その会話内容は、1回目はバスマットの生地や色、2回目は子供のおもちゃ箱の色を相談されてアドバイスをし、Bはよく寝ていると言っており、3回目は、Bの姉がさっき寝たと言っており、いずれも不自然な様子はなかった。
ウ 被告人の供述によれば、Aが外出中、Bを寝かせた寝室には、静かだったので寝ていると思い、確認しに行っていない。洋室でBの姉とテレビを見たり、遊び相手をしたりし、前記のとおり電話で話したほか、ベランダで何度かたばこを吸った。Bの姉を寝室の布団に寝かせたが、Bは寝ていると思い、顔を見て確認はせず、その後は、洋室でテレビを見ていたというのである。
エ Aが帰宅後、同女と被告人は、洋室で、約20分間、買ってきた物の話などの雑談をし、その間の午後4時56分、被告人は、Aの姉と電話をし、今日も孫の顔を見に来ているとか、体調のことを話しており、不自然な点はなかった。
オ 被告人は、本件当時66歳、身長は146cm、体重は42kg(当審第4回公判における被告人質問では、これは原審公判時の体重で、本件当時は37kg強であったと述べる。)であった。
(2)検討
ア 被告人は、普段から粗暴であったとはうかがわれず(相当以前に、夫婦げんかの際に、行き過ぎた行動に出たことは自認しているが。)、犯罪とは無縁であり、もとより粗暴犯前科もない。
イ そのような被告人が、本件当日、孫の顔を見に行きたいと思って、自分から電話をかけた際に、そうであれば外出する間、面倒を見てほしいとAから頼まれたため、短時間、Bらの面倒をみることを引受けたものである。頻繁に本件マンションに訪れていたとしても、同居してBといつも一緒にいるとか、日常的に子守りをさせられているとかいうような、育児ストレスを抱えているような状況にはなかった。
また、その間の様子も、外出先にいるAと3回も電話をして、普通に他愛もない会話をしており、Aが被告人の挙動に不審を抱くような様子は全くない。帰宅後、Bの様子がおかしいことにAが気付くまでの間も、普段と変わらない様子であり、何か後ろめたさを感じているような素振りもない。
そして、被告人が来てから本件発覚までは3時間弱、被告人がBとその姉の3人だけになっていたのは僅か1時間半ほどと短時間であり、しかも、Bは、Aが外出するときには、既に被告人によってベビーベッドに寝かしつけられていた。
なお、Bの姉は2歳であり、本件傷害を起こし得るような行為をすることは、体力的にみて明らかに困難である。
ウ このような被告人の立場や本件当時の状況に照らすと、被告人には、Bが泣き止まないことなどに苛立ちや怒りを抱くといった児童虐待事案に見られるような動機が見当たらず、家庭環境的な虐待のリスクもうかがわれず、Bを揺さぶったことをうかがわせるような事情は見当たらない。
また、原審におけるC証言によれば、工学研究からは、本件傷害を来すような揺さぶり行為は、成人が、少なくとも5cmの振り幅で、1秒間に3往復という速さで、少なくとも数秒間、揺さぶること以外の事を考えずに勢いよく揺さぶった状態、そのような全力でやらない限り、起こり得ないとされている(原審C13、14)。また、Bの体重からすると、成人女性でも、立った状態で揺さぶって、なおかつ、どこかに体を設置させて、そこに体重を支えさせた状態で揺さぶり行為を加えたとすると、あり得るという(原審C17)。このような架橋静脈断裂に必要と想定されるだけの速さや勢いの揺さぶり行為を、立って、どこかに体を設置させて体重を支えさせた状態で、被告人がBに対して行うということが現実的に想定できるか、かなり疑問である。被告人の年齢、体格からくる体力を考えても、前述の被告人の立場や経緯、本件現場の状況等に照らしても、被告人がこのような揺さぶり行為に及ぶと考えるのは、相当不自然である。
エ これらに照らすと、社会的な事実として、被告人がBに対し、公訴事実記載の揺さぶりなど頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行に及んだとすることには、多大な疑問がある。
オ 原判決は、これらの点についても、結局は、被告人がBに対して暴行を加えたことと矛盾しない、暴行を加えることが著しく困難ではないといった形で、被告人の暴行を認めることについての疑問とは評価しなかった。これは、やはり少なくとも不自然であり、当審での審理をも含めれば、経験則に照らし不合理といえる。
原判決は、客観的に外力によるものとの前提で、外力を加えられるのは被告人しかいないと認定すれば、物理的に不可能に近いといった形の反証がない限り、被告人を犯人と認めざるを得ず、このような状況は認定の障害にはなり得ないと考えたものと思われる。
カ 本件は、客観的な事情から、Bの症状が外力によるものとすることもできないし、被告人とBの関係、経緯、体力等といった事情から、被告人がBに暴行を加えると推認できるような事情もない。むしろ、医学的視点以外からの考察では、被告人がBに暴行を加えることを一般的には想定し難い事件であったといえる。
キ それにもかかわらず、被告人が有罪とされ、しかも、経緯において同情し得る事情がないとして、懲役5年6月という相当に重い刑に処せられたのは、原判決が、当事者の意見を踏まえてのことではあるが、Bの症状が外力によるものであるとの前提で、いわゆる消去法的に犯人を特定する認定方法をとったからにほかならない。このような認定方法が、一般的な認定方法として承認されていることは事実である。しかし、本件をみると、そこには、一見客観的に十分な基礎を有しているようにみえる事柄・見解であっても、誤る危険が内在していること、消去法的な認定は、一定の条件を除けば、その被告人が犯人であることを示す積極的な証拠や事実が認められなくても、犯人として特定してしまうという手法であること、さらには、その両者が単純に結びつくと、とりわけ、事件性が問題となる事案であるのに、その点につき十分検討するだけの審理がなされず、犯人性だけが問題とされると、被告人側の反証はほぼ実効性のないものと化し、有罪認定が避け難いこと、といった、刑事裁判の事実認定上極めて重大な問題を提起しているように思われる。
第5 結論
以上の次第であり、原判決は、当審での事実取調べの結果も併せれば、Bの症状の原因が外傷によるものであることを前提とした点においても、弁護人の主張に対する判断として、医学的視点以外の事情を検討した内容においても、論理則、経験則に照らして不合理であり、さらに、Bの症状の原因は、内因性の脳静脈洞血栓症とDICであった可能性が具体的に認められる。
被告人が、Bに対し、揺さぶりなど頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えた犯人であるとした原審の認定には、合理的な疑いが生じている。事実誤認の論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。
第6 破棄自判
そこで、刑訴法397条1項、382条により原判決を破棄した上、同法400条ただし書により、被告事件について、更に次のとおり判決する。
本件公訴事実の要旨は、前記第2のとおりであるが、これまで説明したとおり、公訴事実については犯罪の証明がないから、刑訴法336条後段により被告人に対し無罪の言渡しをすることとし、主文のとおり判決する。
令和元年10月25日
大阪高等裁判所第6刑事部
裁判長裁判官 村山浩昭
裁判官 畑口泰成
裁判官 宇田美穂