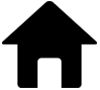平成30年3月14日大阪地裁一部無罪判決(傷害致死)
主文
平成28年3月25日付け起訴記載の公訴事実については、被告人は無罪
理由
(一部無罪の理由)
1 争点等
平成二八年三月二五日付け起訴状記載の公訴事実は、「被告人は、平成二〇年(なお、以下で示す日時は、特に記載のない限り全て平成二〇年のものである。)一二月一一日午後九時頃から同月一二日午前〇時二五分頃までの間に、大阪市《番地等略》M3マンションXXX号室の当時の被告人方において、V2 (当時一歳一一か月)に対し、その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え、よって、同人に急性硬膜下血腫•脳腫脹の傷害を負わせ、同月一四日午後〇時五分頃、同市△△区内の病院において、同人を前記傷害に基づく遷延性中枢神経機能障害により死亡させた。」というものである。
当裁判所は、上記公訴事実中、被告人が、V2に対し、その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えたことが証拠に基づき常識的に考えて間違いないとはいえないと判断したので、その理由を説明する。
2 前提となる事実
V2の死因となった遷延性中枢神経機能障害が、搬送先の病院で一二月一二日午前二時二八分頃撮影されたV2の頭部のCT画像(以下「本件CT画像」という。)上認められる急性硬膜下血腫(以下「本件急性硬膜下血腫」という。)及び脳腫脹の傷害に起因することは、証拠《略》から明らかに認められ、当事者間に争いはない。そして、証人D7及び同D2は、本件CT画像上血腫の色調がまだら状になっており、本件急性硬膜下血腫の中に血液が固まりきっていない部分があることを理由に、V2が本件急性硬膜下血腫を発症したのは本件CT画像が撮影された二、三時間前ないし数時間前であり、その後意識清明期はなく急速に進行したと考えられ、発症後に歩いたり笑顔を見せたりすることは考えられない旨供述する。また、証人D5も、意識清明期があった可能性があると述べる一方で、本件の症状では意識清明期が なかった可能性の方が大きいと述べ、最終的には証人D2の見解に賛同しているともみられる。これらからすれば、本件急性硬膜下血腫の発症時期は、本件CT画像が撮影された同日午前二時二八分頃の二、三時間前ないし数時間前であったと認められる。さらに、同月一一日午後一〇時頃から午後一一時頃までの間に当時の被告人方を訪れたマッサージ師が、V2が被告人から呼ばれて一人で歩いてきたり、せき込んで吸引器を吸ったりしている状況を目撃していることも考え合わせると、V2が本件急性硬膜下血腫を発症したのは、上記マッサージ師が当時の被告人方を退出した同日午後一一時頃から、被告人がV2の異変に対応してH1病院に電話した同月一二日午前〇時二五分頃までの間と認められる。
そして、この時間帯には、被告人とV2は当時の被告人方に二人でいたと認められるが、その際、被告人がV2の頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えたことを示す直接的な証拠はないから、V2の受傷状況等の間接事実から、被告人がこのような暴行を加えたと間違いなくいえるか否かを検討する。
3 各間接事実の検討
(1)まず、検察官は、本件急性硬膜下血腫は、急速に進行した最重度のものであったとした上で、この傷害の程度からすれば、偶発的な事故では生じ得ない、相当に強い外力が働いたといえるから、本件急性硬膜下血腫の原因は他者の故意行為であると主張する。
確かに、本件急性硬膜下血腫及び脳腫脹の程度が重く、V2は一二月一二日午前〇時三六分頃に当時の被告人方を出発して医療機関に搬送されたが、搬送時点で既にV2を救命できた可能性が非常に低かったことについて証人D2及び同D5の供述は一致しており、実際にV2がこれらの傷害を原因として死亡していることからしても、V2の容態が重篤なものであったことは明らかである。
一方、証拠(証人D2及び同D5の供述)によれば、本件急性硬膜下血腫の原因は、頭部に外力が加わったことにより、二本の架橋静脈が破綻したことにあると認められ、また、証人D5の供述によれば、架橋静脈は太い血管であるため、損傷すると出血量は多量になり、血腫も広範囲に及ぶことが認められる。このような本件急性硬膜下血腫が生じたメカニズムに照らせば、血腫の大きさや出血量だけで外力の大きさを推測するのは不十分であり、架橋静脈が損傷するためにはどの程度の外力が必要であるかという観点からの検討が求められることとなる。
そして、証人D5は、小児の架橋静脈は成人と異なり頭蓋骨に対して直角に近い形で通っている上、その血管壁は成人のものよりも薄いことから、脳実質に回転力がかけられた場合には切れやすいと述べ、本件急性硬膜下血腫を生じさせた原因としては、故意による打撃のほか、転倒等の事故も考えられる旨供述する。証人D5は、小児脳神経外科に在籍していたこともある脳神経外科医として、脳の構造や小児の頭部等の特徴について高度の専門的知識を有していることや、その説明内容に不合理な点がなく、供述の信用性に疑いを生じさせる証拠もない(証人D2も、小児の血管壁が相対的に薄いことや、直角に近い形で通っていることについては、認める供述をしている。)こと、実際に、V2の頭部に頭蓋骨骨折はなく、 加えられた外力が頭蓋骨を骨折させるほどに強いものではなかったこと等からすれば、証人D5の上記供述は信用できる。そうすると、本件急性硬膜下血腫の進行速度や程度から、加えられた外力が他者の故意行為によるものと認めることはできない。
なお、証人D7及び同D2も、本件CT画像から認められる本件急性硬膜下血腫の程度のみを理由に、その原因が他者の故意行為によるものと供述しているわけではないとも解される。
以上によれば、本件急性硬膜下血腫が最重度のものであったことから、これが他者の故意行為を原因とするものであると認めることはできない。
(2)また、検察官は、証人D7及び同D2の医師としての過去の経験上、偶発的に受傷した急性硬膜下血腫により死亡した例はないことも、本件急性硬膜下血腫等の原因が他者の故意行為であることの根拠の一つとして主張する。
しかし、検察官の主張は、あくまで証人D7及び同D2の二名の経験に依拠するものであり、前記(1)で述べた本件急性硬膜下血腫が生じたメカニズムや証人D5の供述内容からすれば、死亡結果が生じる程度の急性硬膜下血腫が偶発的事故により発生する可能性も十分にあるといえる。実際にも、転倒時の偶発的に事故によって生じた急性硬膜下血腫により死亡した症例が報告されていること等も踏まえると、検察官主張の点は、偶発的な事故では死亡結果は発生しないことを認めるに足りるものではない。
(3)ア そして、検察官は、V2の頭部等に多数の皮下出血があることからすれば、V2の頭部に対して故意の外力が何度も働いたといえるから、本件急性硬膜下血腫の原因についても他者の故意行為によるものと認められると主張する。
イ 証拠《略》によれば、V2の遺体の頭部にはおおむね八か所の皮下出血等(以下「本件皮下出血」という。)があったことが認められ、これらのうちの少なくとも一つは、本件急性硬膜下血腫を生じさせた外力により生じたものと考えられる。しかし、証拠上、そのうちのいずれが本件急性硬膜下血腫が生じた際のものであるかを特定することはできない。
なお、証人D2は、本件皮下出血は、いずれも外力の作用によるものであると供述する一方、証人D5は、額部、右後頭部及び眼窩部以外の皮下出血については、搬送時のカルテ等では確認できないことから、それらについては搬送後に血圧が低下したことによる多臓器不全に伴う血管透過性亢進等により生じたものである可能性がある旨供述する。証人D5は臨床医であり、遺体の状況から受傷原因を推察する専門家ではないところ、本件においても、本件皮下出血の状態等からではなく、客観的記録に残っていない 皮下出血を説明する可能性として、血管透過性亢進等の影響を指摘しているものと考えられる。しかし、救急医療におけるカルテは、治療を目的として作成されるものであるし、V2を診察した証人D7が、搬送時に額の皮下出血に気付かなかったことや、頭部の皮下出血の多くが有髪部や髪際部にあり、遺体にみられた皮下出血のいずれもが必ずしも外表から容易に観察可能であったとは限らないことから、本件皮下出血の一部について記載がなかったとしても、これらが存在しなかったことを示すものとは必ずしもいえない。また、D5供述から認められる血管透過性亢進のメカニズムに照らせば、搬送後死亡までの時間に血管透過性亢進によって皮下出血が生じたことと本件皮下出血が解剖時に「吸収に傾く」(治癒に向かう)と判断されていることとの整合性や、上記メカニズムと本件皮下出血の形状との整合性は明らかでない。何より、皮下出血の原因について専門的知識を有する法医学者である証人D2は、本件皮下出血が血管透過性亢進等によるものであることを明確に否定している。そうすると、証人D5が指摘する可能性は、抽象的なものにすぎず、本件皮下出血は、証人D2の供述するとおり、全て外力の作用によるものであると認められる。
また、証人D5は、対側損傷の可能性を理由に、右後頭部の帽状腱膜下出血が致命傷によるものであると供述する。しかし、この見解は、そもそも、外力の作用により生じた皮下出血が上記三か所に限られることを前提とするものである。また、前記(1)のとおり、本件急性硬膜下血腫が頭頂部付近にある架橋静脈の破綻により生じたという発症メカニズムに照らせば、皮下出血が生じた場所又はその対側に血腫が現れるとは必ずしもいえない。以上から、本件急性硬膜下血腫の発症時に受傷した皮下出血が右後頭部のものであると特定することはできない。
ウ 次に、幼児の頭部に、偶発的な事故等によりおおむね八か所もの皮下出血が生じることは通常考えられず、この中に偶発的な事故等で受傷することが想定し難い頭頂部の皮下出血が含まれていることからすれば、本件皮下出血の全てが、偶発的な事故等により受傷したものであるとは考え難い。もっとも、上記のとおり、本件皮下出血のうちのいずれが本件急性硬膜下血腫を生じさせた外力によって生じたかを特定できない以上、その一部に他者の故意行為による皮下出血が含まれているからといって、本件急性硬膜下血腫が他者の故意行為によって生じたとはいえない。また,本件皮下出血はそれぞれが一回の外力によるものと考えられるが、そうであっても、多数の皮下出血があるからといって、直ちに、その全てが他者の故意行為によるものであると推認することはできない。結局、多数の皮下出血があることを根拠に、本件急性硬膜下血腫を生じさせた外力が他者の故意行為によるものであり、更にはそれが被告人によるものと認めるためには、本件皮下出血の相当数が同一機会(前記二に認定した本件急性硬膜下血腫の発症時期)に生じたと、間違いなく認められることが必要というべきである。
エ 証人D2は、本件皮下出血は、治癒作用が始まっている(吸収傾向が認められる。)こと等からすると、死亡する二、三日前に受傷したものであると考えられ、また、各皮下出血の色調や出血の状況等に大きな差異がないこと等からすると、全て同じ時期に生じたと考えても矛盾はなく、発症した時間帯に幅があるとしても半日程度である旨供述する。しかし、V2が、搬送後、二日ないし二日半の間治療を受けた後に死亡したことや、その解剖所見上、頭部及び顔面の皮下出血のほとんどについて、「吸収に傾く」 「やや陳旧な」と皮下出血の進行程度について解釈に幅のあり得る記載がされていること、これらのうち、少なくとも左眼窩部の皮下出血については、V2の実母である証人P3が、一一月二七日頃にV2が 額に負った皮下出血が下りてきたものであり、本件の三日前頃にはH1病院で症状の確認を求めた旨供述しており、一二月一一日以前に生じたものである可能性があることや、同日午後七時三〇分頃及び午後九時一分頃にV2の顔面を撮影した二枚の写真には、左眼窩部のみならず右眼窩部にもあざ様のものが写っていることからすれば、証人D2が専門的知識を有する経験豊富な法医学者であることを考慮しても、受傷時期を上記供述のとおりに特定できるのかどうかには疑問が残る。この点を措くとしても、D2供述によっても、各皮下出血の受傷時期については、半日程度の幅が残ることとなる。これらからすると、D2 供述のみを根拠にして、本件皮下出血の相当数が同一機会に生じたと認めることはできない。なお、証人 D2は、本件皮下出血が点在していること等から、偶発的なものではなく他者の故意行為によるものと考えられると供述するが、皮下出血の点在だけからこれら全てが他者の故意行為によるものにほかならないということはできず、この見解も本件皮下出血が同じ機会に生じたことを前提とするものと解される。
一方、証人P3は、一二月一一日午後八時頃に出勤する時点で、V2の左眼窩部の皮下出血以外の皮下出血については認識していなかった旨供述しており、上記二枚の写真には、左眼窩部及び右眼窩部のあざ様のもの以外に傷や内出血は写っていない。他方、証人P3や被告人の実母である証人P4が、搬送後間もなく病院でV2の額付近に傷があったのを見た旨供述しており、証人D7も、後日、V2の写真で、左前額部の傷を確認した旨供述していることからすれば、左前額部の二か所の皮下出血については、P3が出勤してからV2が搬送されるまでの間に生じたものであると認められる。しかし、これら以外の頭部の皮下出血は、いずれも髪際部や有髪部のものであり、一見して見える場所の皮下出血ではない。また、P 3が、当時、昼夜働きに出ていたことや、V2を風呂に入れるなどしてV2の身体の状態を確認していたとは供述していないこと等からすると、P3が頭部の皮下出血の存在に気付いていなかった可能性は否定できない。すなわち、証人P3の供述等によっても、本件皮下出血の相当数が一二月一一日午後八時頃以降に生じたと認めることはできない。
また、被告人は、前記のとおり一二月一一日午後一〇時頃から午後一一時頃まで当時の被告人方にマッサージ師を呼び、同人にV2を見せているところ、本件皮下出血の多くがそれまでに発生しており、被告人がそれらについて認識していたのであれば、わざわざ怪我をしているV2をマッサージ師に見せることは不自然であるとも思える。しかし、本件皮下出血が上記時間帯以前に生じていたとしても、上記のとおり、左前額部以外の皮下出血は、いずれも目立たない場所のものであって、母親であるP3すら気付いていなかったものであることからすれば、被告人自身も気付いていなかった可能性がある。いずれにせよ、 本件皮下出血の多くが既に発生していたとしても、被告人がその日だけ訪問してきたマッサージ師にV2 を見せたことが格別不自然であるとはいえない。
オ そうすると、本件皮下出血の相当数が前記二で認めた本件急性硬膜下血腫の発症時期に受傷したものであることが、間違いないといえる程度にまで立証されているとはいえない。例えば、本件皮下出血の一部が一二月一一日の同発症時期以前の時間帯(D2供述にいう半日程度のうち)に、他者の故意行為により、又は偶発的に、生じていたところ、同発症時期に本件急性硬膜下血腫を発生させた外力が左前額部等に偶発的に加わった可能性は残るといわざるを得ない。そうである以上、V2の頭部に複数の皮下出血があることを理由に、本件急性硬膜下血腫が被告人の故意行為を原因とするものであると推認することはできない。
(4)以上のとおり、証拠上認められる間接事実を総合しても、本件急性硬膜下血腫が他者の故意行為によって発生したことが常識的に考えて間違いないとはいえない。したがって、被告人が、V2に対し、前記公訴事実にいう、その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えたことが、常識的に考えて間違いないということはできない。
なお、V2には網膜出血が見られるが、証人D2の供述によっても、他者の揺さぶり行為によって生じた可能性があるというにとどまり、しかもその時期も明らかでないから、上記網膜出血の点から、被告人が前記公訴事実の期間にV2の頭部に暴行を加えたと認めることはできない。
4 よって、結局、平成二八年三月二五日付け起訴状記載の公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法三三六条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
平成30年3月14日
大阪地方裁判所刑事第15部
裁判長裁判官 増田啓祐
裁判官 三澤節史
裁判官 宮崎沙織