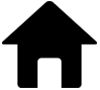令和2年12月4日大阪地裁無罪判決(傷害 揺さぶり疑い)
主文
被告人は無罪。
理由
1 本件公訴事実は、「被告人は、平成29年6月26日午後2時40分頃から同月27日午前8時3分頃までの間、大阪府〇〇市内又はその周辺において、長男であるA(当時4か月)に対し、その身体を揺さぶるなどの方法により、その頭部に衝撃を与える暴行を加え、よって、同人に全治不明の急性硬膜下血腫、両側眼底出血の傷害を負わせたものである。」というものである。
当裁判所は、被告人が、Aに対し、公訴事実記載の時点における上記暴行(以下「公訴事実記載の暴行」という。)を加えたと認定するには合理的な疑いを差し挟む余地があると判断したので、以下、その理由を説明する。
2 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)被告人は、平成29年2月〇日(以下の日付は平成29年のものをいうのでその記載を略する。)、B病院において、Aを出産し、退院後は大阪府〇〇市内の自宅で夫及びAと生活していた。被告人は、6月、同市内にある託児所にAを昼間預けるようになったが、同月26日は、午後2時40分頃にAを抱っこひもを用いて縦抱きにした状態で自転車に乗り、託児所から帰宅した。
(2)被告人は、前記のような状態で自転車に乗り、同月27日午前7時52分頃から午前8時3分頃の間にAを託児所に預けた。同日午前8時50分頃、Aが、硬直させた両腕を伸ばして振り回すような動作をするといった異変を示したため、託児所の園長が被告人に連絡をし、被告人は、同日午前9時34分頃、託児所からAを引き取って、B病院に受診させ、Aはそのまま入院した。
(3)同日、B病院において、Aの頭部に新旧の硬膜下血腫を認めたが、外傷や頭蓋底、頭蓋骨の骨折は認めなかった。また、翌28日には、同病院において、Aの両眼に眼底出血(両眼の広範にわたる網膜出血)を認めた。
(4)Aは、虐待の可能性があるとして、同日、大阪府〇〇子ども家庭センターに保護されるとともに、C病院に転院した。
なお、Aの脳には、脳実質損傷がなく、画像上捉えられるような脳浮腫もなかった。また、脳に影響を与えるような事情(代謝疾患、遺伝疾患、感染症、先天奇形、低酸素性脳症、水頭症等)を疑わせるものはなかった。
3(1)検察官は、C病院の小児科医であるD医師がAの大脳半球間裂及び左後頭部に急性硬膜下血腫、左右両側に慢性硬膜下血腫が認められる旨証言するところ、小児脳神経外科医であるE医師及び小児脳神経外科医であるF医師もAの頭部外傷の状況についてほぼ同内容の証言をしていて、Aの頭部の受傷状況について争いはないとした上で、E医師やD医師の証言を引用して、Aには急性硬膜下血腫が存在するから、Aの身体を揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行が加えられたことが推認される旨主張する。
(2)F医師は、Aの前頭部から頭頂部、後頭部にかけて脳全体を覆うように慢性硬膜下血腫が存在し、また、大脳半球間裂から円蓋部(左側後頭部)に急性硬膜下血腫が存在するが、大脳半球間裂の頭頂部付近においては、大脳半球間裂の部分とつながる形で伸びる急性硬膜下血腫が左脳を覆う慢性硬膜下血腫の上部(頭頂寄り)に覆いかぶさるようにして存在したと証言する。
このF医師の証言は、Aの入院先において撮影された水平断(軸位断。地面と水平(平行)に頭部を輪切りにする断面図)、矢状断(頭部の前後を結ぶ線で地面に対して垂直に切る断面図)、冠状断(耳と耳をつなぐ線で、顔面と水平な面を切り出す断面図)のCT画像及びMRI画像を元に、立体的な視点から総合的に脳全体の各硬膜下血腫の形状及び位置関係について平明に説明するものである。D医師は、弁護人からの反対尋問の際には、頭頂部で急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫が隣接することなどを認めていて、これに反する内容を証言しているとは解されない。また、E医師は、慢性硬膜下血腫について、脳の両側の前頭部から側頭部、頭頂部にあり、急性硬膜下血腫とは離れて存在する旨証言するが、同証言は、検察官が示した水平断のCT画像及びMRI画像を前提に判断した内容であるところ、弁護人からの反対尋問の際には、冠状断のCT画像を踏まえて、頭頂部付近で急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫が隣接している状態であると認めていることからして、Aの脳全体を正確に把握した上でのものではなく、一部画像のみに基づく判断であることがうかがわれ、これは採用の限りでない(E医師作成の鑑定書についても同様である。)。
そうすると、Aの頭部の受傷状況は、F医師の証言を前提とすべきであると認められ、これを前提にAの受傷機序を判断することの妨げとなるべきものはない。
(3)Aの急性硬膜下血腫の発生機序について、E医師は、慢性硬膜下血腫が前頭部から頭頂部、一部側頭部にかかっていること、急性硬膜下血腫は後頭部にあることを前提に、慢性硬膜下血腫の存在により脳は後方に押され、急性硬膜下血腫のある部位の架橋静脈は押し付けられており、伸展されてはいないため、慢性硬膜下血腫とは別に急性硬膜下血腫が発生した旨説明しつつ、急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫は離れて存在しているので、慢性硬膜下血腫が原因で急性硬膜下血腫ができたということは考えにくく、直接の外傷がないのであれば、頭が前後に揺れるとか、いわゆる回転加速度が原因となって、頭蓋の動きと脳の動きがずれ、架橋静脈が伸ばされて切れたと考えられる旨証言し、また、D医師も、内科的な疾患が考えられないことから、何らかの強い外力が働いたと考えられるが、眼底出血がありつつも骨折等の外傷がないことを踏まえると、強い力で前後左右に揺さぶられるような力であったり、表面が傷つかない形での柔らかいものに何度も頭をぶつける形であるとかいうような外力が働いた可能性が高い旨説明しつつ、慢性硬膜下血腫の一番厚みのある部分である側頭部の架橋静脈が一番伸展されやすいが、急性硬膜下血腫のある部位はその部分と合致していないため、架橋静脈が伸展されて出血したとは考えにくい旨証言する。
しかしながら、この点に関する両医師の各証言については、前記のとおり、その前提とするAの頭部の受傷状況の把握が必ずしも正確でないことが弁護人からの反対尋問によって明らかにされている。両医師は、急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫が隣接しているとしても、これは急性硬膜下血腫による出血が移動してきたものであるという趣旨の証言をするが、いずれも急性硬膜下血腫の出血点について述べていない上、E医師が、後頭部で出血したものが前頭部に移動したと述べるのに対し、D医師は、大脳半球間裂の出血が後頭部に回り込んで広がった旨述べるなど、その見解も相違していて、やはりそのまま採用できるものではない。
この点、F医師は、急性硬膜下血腫は架橋静脈の破断によって生じたと考えられるが、慢性硬膜下血腫が前頭部、頭頂部、後頭部にかけて広範囲に存在している状況下では、架橋静脈が存在する箇所全体が伸展されていると考えるのが適当であり、伸展された架橋静脈は通常よりも断裂しやすく、より軽微、軽度な外力によって破断する、AのCT画像及びMRI画像を見ると、頭頂部の右側では、架橋静脈が伸展している様子を確認できるのに対し、左側には、架橋静脈が確認できず、その付近が出血点であると考えられると証言する。
このF医師の証言は、CT画像及びMRI画像に裏付けられた説得的なものである上、急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫の位置関係や血腫の拡大状況等についての説明ともよく整合し、信用できるものであり、少なくとも排斥することは困難であって、検察官が主張する身体を揺さぶるなどの方法によりその頭部に衝撃を与える暴行とは異なる、より軽微、軽度な外力により、伸展された頭頂部の架橋静脈が破断し、同箇所を出血点として、急性硬膜下血腫が大脳半球間裂(頭頂部)から後頭部の方へ広がり、後頭部で左側に広がったとの具体的な可能性を示すものといえる。
(4)このように、本件は、子供の頭部に単に急性硬膜下血腫が存在する事案ではないのであって、既に慢性硬膜下血腫が存在し、かつ、これが急性硬膜下血腫と隣接している部分がある事案であることを直視したとき、急性硬膜下血腫が公訴事実記載の暴行に至らない外力によって生じたのではないかとの疑問が払拭できない。
その外力として証拠上想定されるものとしては、例えば、弁護人が主張する、被告人が、6月26日及び翌27日、Aにつき抱っこひもを用い、自転車に乗って託児所に送迎したことにより生じた外力であっても、首の据わらない子供に対し体調を損なうおそれがあるとされている縦抱きの状態で、抱っこひもに付属していたヘッドサポートを使用していなかったというのであるから、その現実的な可能性を打ち消すほどの理由は見いだし難い。外力が小さいものであった可能性は、E医師が、Aには外傷が強い場合に出てくる脳浮腫が認められず、急性硬膜下血腫も軽度のものであった旨証言することと整合し、また、F医師も、Aには脳実質損傷も脳浮腫も認められないが、激しい暴力的な揺さぶりが加えられた場合には、即時に意識障害が認められるものである旨証言するところ、被告人がAを託児所に預けた時点では、Aに意識障害等は認められず、その約50分後に異変が生じたこととも整合する。
(5)検察官の主張に沿って、急性硬膜下血腫の存在から、身体を揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行が加えられたと直ちに認定することには、疑問があるといわざるを得ない。検察官の主張は、D医師、E医師及びF医師の証言がほぼ同内容であることを前提に、Aの頭部の受傷状況について争いはないとした上で論理を組み立てるもので、いささか粗いきらいがある。
4(1)検察官は、被害児に病気がなく、事故で頭部に致死的な外力が加わった場合でなければ、頭部が激しく揺れる状態になったこと(揺さぶられっ子症候群)以外考えられないとする小児眼科医であるG医師の証言を引用し、同医師が頭部外傷の認められる小児に関しては特に高度な専門的知見を有する専門医であることや、その証言内容が、眼球の解剖学的な特徴、眼底検査の手法に踏み込みつつ、Aに認められた眼底出血の受傷原因について、内因性疾患、頭蓋内圧の亢進等の他の可能性を検討して鑑別した上で揺さぶられっ子症候群による眼底出血との結論に至っており、合理的かつ具体的な内容であって非常に説得力に富むこと等を指摘し、G医師の証言には高度の信用性が認められるから、急性硬膜下血腫に加えて多層性・多発性の眼底出血がAに認められた事実が、Aの身体を揺さぶるなどの方法によりその頭部に衝撃を与える暴行の存在を強く推認させると主張する。
(2)Aの両眼の受傷状況について、G医師は、6月28日午後4時頃の時点で、Aの右眼底には、軽度の乳頭腫脹、乳頭から広がる網膜出血、黄斑部をほぼ覆う形の網膜上出血、乳頭周囲の神経表層の出血があり、また、網膜出血後の吸収過程において生じる硬性白斑が複数認められ、左眼底にも、乳頭腫脹と乳頭周囲出血、乳頭から広がる網膜出血、視神経周囲の神経表層の出血がある旨証言する。この証言に疑問をいれるものはなく、そのように認められる。
(3)この受傷状況を前提に、G医師は、Aの眼底出血は、網膜の前、網膜の表層(表在性)、網膜の内部にわたる多層性・多発性の出血であるところ、Aに病気がなく、同乗する第三者が死に至るような交通事故や、即死するような大きなものが頭を直撃するような落下事故でもない場合には、その眼底出血から揺さぶられっ子症候群による網膜出血が考えられる旨、その機序としては、子供の頭部が激しく揺れるような状態になったときに、眼球の中にある硝子体が大きく動き、硝子体と網膜の付着部から力が伝わり、網膜の血管が牽引されたり、押されたりという動きを繰り返して、破綻して出血したと考えられる旨、多層性・多発性の眼底出血は、頭蓋内圧が上がったことだけでは生じず、日常生活では決して起きないから、自転車乗車時の縦揺れは原因とならず、硬性白斑を除き、Aの眼底出血は1回の機会によるものと考えられる旨、受傷時期は眼底の写真が撮影された時期を基準に1日、2日、遅くても3日の範囲内で、多分1日、2日の話であるなどと証言する。そして、硝子体に加わる加速、減速の力の程度に関しては、G医師は、硬膜下血腫が認められる被害児には、その重症度から必ず網膜出血も出てくるので、硬膜下血腫に達する外力の閾値が、網膜出血に必要な最低限の閾値であると解釈していると証言する。
この点、臨床現場として、硬膜下血腫が認められた子供について眼底検査を依頼される数は多いが、実際に網膜出血が認められたことは珍しいとG医師自身が証言していることからすれば、G医師の硝子体に加わる加速、減速の力の程度に関する前記証言は、G医師が、専門医としての研究に基づく知見を前提に、硬膜下血腫が認められる子供を対象に眼底検査を実施する臨床医としての経験則に主に依拠したものといえる。そのため、G医師が見解を支える上で重視するものとして証言中で触れた三つの論文は本件を考察する上で十分なものなのか(一つ目の論文においてくみ取るべきは客観的なデータだけであるべきではないのか、データ数としても絶対的に母数が少ないのではないか、二つ目の論文において論じられている網膜ひだは本件で確認されておらず、前提として必要な条件設定を曖昧にしていないか、三つ目の論文はキツツキについて論じたものであるが、なぜ参考になるのか等)、G医師の専門医としての研究は反対の立場の説をどの程度検討したものなのかといった、弁護人が抱いた疑問はひとまず措いたとしても、G証言によっても、硬膜下血腫が存在しない子供について、多層性・多発性の眼底出血が認められた場合に、当該子供の頭部に外力が加えられたか、また、加えられたとして、どの程度の外力であったのかを、どの程度推認できるかは判然としていないとみる余地が残されているといわざるを得ない。G医師自身、多層性・多発性の網膜出血が生じるための外力の程度について数値を計測した研究はなく、目に対する工学モデルが研究されていないと証言している。眼球内部の硝子体が網膜(ないしその血管)を牽引するほどの外力とはどの程度のものなのか、また、その外力が子供の頭部に加えられた場合に、脳にはどのような影響が生じるのか(硬膜下血腫や脳挫傷、脳浮腫等の症状は伴うのか)といった点については、必ずしも明らかなものとなってはいない。
また、G医師の証言のうち、多層性・多発性の出血であるとの評価の前提部分である、硬性白斑を除きAの眼底出血は1回の機会によるものと考えられるとする部分についても、別の理解が可能である。すなわち、G医師は、深層の網膜出血が時間の経過により表層の出血になる(移動する)ことはないと説明しながらも、表在性出血が網膜前出血に移動することや網膜前出血が拡散していくことは否定しておらず、また、Aの網膜内出血はすぐに消え、網膜表層のはけ状の出血も大きさにはよるがすぐに消えると考えられるが、その早さについては個人差があると前置きした上で、網膜出血が吸収されていく過程で、一部の層の出血が吸収を終えたため、元々多層性であったものが単層性に見えることがあることは否定しない。このような証言を前提として、少なくとも、G医師が一体として評価する網膜の前、網膜の表層(表在性)、網膜の内部の各出血とは別に、受傷時期が異なることが明らかな出血(の跡である硬性白斑)が存在していることなどを踏まえると、Aの眼底写真が撮影された6月28日午後4時以前に発生していた表在性出血が網膜前出血へと一部移動した可能性や、硬性白斑の受傷時期とは異なる時期に生じた眼底出血の吸収過程の名残がいずれかの層に残存している可能性を指摘でき、硬性白斑を除きAの眼底出血は1回の機会によるものと考えられるとする部分のG証言を、絶対的なものとみてよいか確信するに至らない。
さらに、G証言のみによっては、眼底出血の受傷時期を公訴事実記載の時点に限ることはできない。
(4)以上によれば、検察官が主張するように、Aに眼底出血が認められるにしても、それ自体で、公訴事実記載の暴行の存在を認定させるものとは断じられず、また、急性硬膜下血腫の存在が有する推認力と相俟っても、公訴事実記載の暴行の存在を認定させるものとみることははばかられるというほかない。
5 以上のとおり、公訴事実記載の暴行があったと認定するには合理的な疑いを差し挟む余地がある。
なお、検察官は、F医師が、自宅での軽微な外傷、あやし行為、ヘッドバンキング等により急性硬膜下血腫が生じた症例をもとに、本件においても慢性硬膜下血腫の存在により架橋静脈が伸展していたたため、弱い外力によって破断しやすい状況であり、自転車乗車時の縦揺れで破断してもおかしくない、一般的なあやし行為によっても眼底出血が生じた事例がある、などと証言したのに対し、〔1〕本件とは前提条件が異なる症例を引き合いに出している上、〔2〕専ら被告人の説明に基づく再現精度の判然としない動画の中の人形が揺れる様子を見て、架橋静脈破断の原因となり得る旨証言するのみで、受傷についての抽象的な可能性を指摘するにすぎない、〔3〕E医師、D医師、G医師の各証言とも反する、〔4〕抱っこひもを使用して自転車乗車時に揺れによる頭部外傷が生じた事例の報告例は一切存在しないなどともいう。
しかしながら、強度の暴行を加えずとも急性硬膜下血腫が生じた症例が存在すること自体が、殊に本件のように既に慢性硬膜下血腫が存在していた場合等には、検察官の主張する傷害結果発生の機序を疑わせる一事情となり得るし、このF医師の証言は、架橋静脈が破断するメカニズムを説明するもので、前記動画の揺れのとおりであれば急性硬膜下血腫が生じるという趣旨で必ずしもされたものではなく、被告人が抱っこひもを定められた用法に反した方法で使用してAを自転車で託児所に送迎していたことからすると、自転車乗車時の揺れが受傷原因となり得るとの証言は、単なる抽象的な可能性をいうものとして切捨ててよいかはためらわれ、同様の事例の報告例がないことが同証言を排斥するものとはならない。E医師、D医師、G医師がいずれも専門家として豊富な経験を有していることは確かであるが、E医師、D医師のこの点の証言は感覚的なものにとどまっており、Aのような慢性硬膜下血腫が既に存在する者の場合にどう考えられるのかを論じているものとも認め難い。G医師の眼底出血の点に関する証言についての評価は前記のとおりである。
6(1)なお、検察官は、Aの受傷結果から認められる受傷時期は、6月26日午後0時34分頃から同月27日午前8時52分頃までの間であるところ、同受傷時期内において、被告人のみが犯行に及ぶことが可能であり、かつ、動機となり得る事情等がある上、被告人は、同月28日以後に、Aを虐待したことがあることを示唆する言動を繰り返していたもので、被告人が犯人であることが明らかである旨主張している。
すなわち、〔1〕託児所の園長や保育士、育児補助のため被告人宅を訪れていた可能性のある夫の両親には、Aに暴行を加える動機が存在せず、夫については、Aと二人きりになる時間がごく短時間であった上、育児への関与の程度に照らし、育児によるストレス等の動機となり得る事情は存在しなかったのに対し、被告人は、〔2〕Aの育児を主に担当し、就寝時間以降はAと二人きりになることから、唯一犯行が実行可能な人物であった上、〔3〕3月以降、育児ノイローゼ又は産後うつの傾向があると判断され、精神的に不安定になったこともあり、また、6月21日にはAの哺乳量が増えなければ託児所で預かることは難しいと指摘されるなどしたことに大きなストレスを感じていたところ、同月26日から27日にかけての夜、Aが寝付かず、哺乳もしなかったことから強いストレスを感じ、そのストレスをAにぶつけて発散するという本件犯行の動機となり得る事情があった、〔4〕同月28日、B病院の医師からAの受傷原因の心当たりを聞かれ、「激しくすると機嫌がいいので、最近は夜とかにちょっと激しくゆすったかもしれません。」などと受傷原因に心当たりがあるかのような発言をした、〔5〕同日午後、託児所の園長から、同人がAを病院で検査するよう勧めたのに、そうしなかった理由を尋ねられ、「病院で検査すると児相に連れていかれるから。」と述べ、被告人自らがAの脳等に傷害を負わせたことを強く推認させる発言をした、〔6〕10月頃、夫の母に対し、「自分も一瞬のことやから、やったかもしれない。」と発言するなど、本件犯行を含むAへの虐待を示唆する言動を繰り返している、したがって、被告人が犯人であることは明らかである、というのである。
(2)前記の検察官が主張するAの受傷時期が、公訴事実で主張するそれより幅が広いものとなっていることはさておき、上記の〔1〕から〔6〕に関しても触れておく。
確かに、託児所の園長、保育士及び夫の両親には、動機となり得る事情は考えにくいように思われるにしても、夫については、Aの出生により生活状況が大きく変化し、ストレスを感じていた可能性は否定し得ない上、そもそもストレス発生の原因は育児に限られないことからすると、他の者に動機が存在せず、被告人のみに動機となり得る事情があったなどと軽々にいえるものではない。被告人が、育児につき相当のストレスを感じていたことはうかがわれるものの、そのことをもって暴行に及んだと認定することはいうまでもなく飛躍がある。
被告人が唯一犯行が可能な人物であるといえる理由はない。なお、G医師は、前記のように、眼底出血の受傷時期は、眼底の写真が撮影された時期を基準に1日、2日、遅くても3日の範囲内で、多分1日、2日の話である旨証言する一方で、Aのような小さな網膜内出血を起こすぐらいの揺さぶりであったら、その後普通に保育園に行ったり、普通の日常生活を送っていないはずであると思うと証言するところ、Aの異変が生じた時期からすると、この後者の証言は、被告人が託児所に預けた後に眼底出血に関して受傷したことを意味することとなるのではないかとの疑問はそれとして指摘しておきたい。
6月28日にされた被告人の医師に対する発言については、同医師から、Aに眼底出血が認められ、頭蓋内と眼底両方に出血があることからすると、頭部を激しく揺さぶられたことが原因である可能性が高く、今後の発達に影響が出るかもしれない旨説明された際のものであり、同医師から受けた説明内容を踏まえると、被告人がAの受傷内容について衝撃を受け、医師の説明に沿う状況を見つけ出そうとした可能性や、同医師の想定する、激しく揺さぶられたという程度と異なる内容を想定して回答した可能性も考えられる。同席した夫が、医師に対し、「祖父母も可愛くて高い、高いをしていたようです。」と述べていることからも、その可能性は否定し得ない。託児所の園長に対する被告人の発言については、検察官の主張するようなやり取りがあったのかがまず定かでないし、仮にあったとしても、同月20日から22日まで連日被告人がAをB病院小児科に受診させ、この際、同病院の医師がAに脳検査の必要がないとの意向を示していたことにも照らすと、被告人が虐待を疑われ、Aが保護されたことを報告する中で、気が動転し、問いに対し的確な回答ができない中での発言であるとの理解が可能である(ちなみに、5月のAの健康相談の際に、被告人の返答にややちぐはぐな面がある旨評された証拠がある。)。さらに、夫の母に対する被告人の発言についてであるが、そのようなものがあったとしても、捜査機関から繰り返し取調べを受ける中で、心理的に疲弊し、自身の行動を疑った思いが口にされただけであるとの理解が可能である。
(3)公訴事実記載の暴行を加えた犯人がいるということであったとしても、本件の証拠によっては、被告人が犯人であることは明らかであるとする検察官の主張を採用するには至らない。
7 結局、本件の公訴事実については犯罪の証明がないから、刑事訴訟法336条により、被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑 懲役3年)
令和2年12月4日
大阪地方裁判所第6刑事部
裁判長裁判官 大 寄 淳
裁判官 沖敦子
裁判官 青木崇史