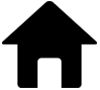平成30年11月14日大阪高裁 逆転無罪判決(医師法違反)
主文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人亀石倫子(主任),同三上岳,同川上博之,同久保田共偉,同白井淳平及び同城水信成共同作成の控訴趣意書及び各控訴趣意補充書に各記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官海津祐司作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。
論旨は,被告人の所為が医師法31条1項1号,17条に該当するとして,被告人を罰金15万円に処した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というものである。
そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。
第1 本件公訴事実及び原判決の判断
1 本件公訴事実の要旨
本件起訴に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,医師でないのに,業として,別表記載のとおり,平成26年7月6日頃から平成27年3月8日頃までの間,大阪府内の「B(店名)」において,4回にわたり,Cほか2名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて前記Cらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたものである。」(別表略)というものであり,適用すべき罰条として,医師法31条1項1号,17条が掲げられている。
2 原判決の判断の概要
原判決は,本件の争点を,①針を取り付けた施術用具を用いて人の皮膚に色素を注入する行為(以下「本件行為」という。)が医師法17条の「医業」の内容となる医行為に当たるか否か,②医師法17条が憲法に違反するか否か,③本件行為に実質的違法性があるか否か,であるとして,後記のとおり,①については,本件行為は医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に該当する,②医師法17条は憲法31条に違反するものではなく,また,本件行為に医師法17条を適用することは憲法22条1項,21条1項,13条のいずれにも違反しない,③本件行為には実質的違法性が認められるとの判断を示し,本件公訴事実どおりに罪となるべき事実を認定した上,本件行為に医師法31条1項1号,17条を適用して被告人を罰金15万円に処したものである。
(1) 本件行為の医行為該当性に関する原判決の判断要旨
ア 原判決は,「医行為」の意義について,医師法17条は,医師の資格のない者が業として医行為を行うこと(医業)を禁止しているところ,これは,無資格者に医業を自由に行わせると保健衛生上の危害を生ずるおそれがあることから,これを禁止し,医学的な知識及び技能を習得して医師免許を得た者に医業を独占させることを通じて,国民の保健衛生上の危害を防止することを目的とした規定であるとし,同条の「医業」の内容である医行為とは,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解すべきである,と説示する。
イ そして,原判決は,医師法17条及び同法1条の趣旨や法体系から,「医行為」とは,①医療及び保健指導に属する行為の中で(医療関連性),②医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為をいうと解すべきであるという弁護人の主張に対し,その主張によれば,医療及び保健指導に属する行為ではないが,医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為(美容整形外科手術等)を医師以外の者が行うことが可能となり,このような解釈が医師法17条の趣旨に適うものとは考えられないし,弁護人の主張は,法体系についての独自の理解を前提とするものであるとして,弁護人の主張を排斥している。
また,「医行為」に関する最高裁の判例(最高裁昭和30年5月24日第3小法廷判決(刑集9巻7号1093頁),同昭和48年9月27日第1小法廷決定(刑集27巻8号1403頁),同平成9年9月30日第1小法廷決定(刑集51巻8号671頁))について,弁護人が,これらの判例によれば,「医行為」の要件として「疾病の治療,予防を目的」とすることが求められていると主張するのに対し,原判決は,上記各判例の事案は,いずれも被告人が疾病の治療ないし予防の目的で行った行為の医行為性が問題となったもので,医行為の要件として上記目的が必要か否かは争点となっておらず,上記各判例はこの点についての判断を示したものではないから,本件において,「医行為」の要件として「疾病の治療,予防の目的」が不要であると解しても,最高裁の判例に反しない旨説示している。
ウ 次いで,原判決は,本件行為の医行為該当性について,被告人が行った施術方法は,タトゥーマシンと呼ばれる施術用具を用い,先端に色素を付けた針を連続的に多数回皮膚内の真皮部分まで突き刺すことで,色素を真皮内に注入し定着させるといういわゆる入れ墨を施すことであり,このような入れ墨は,必然的に皮膚表面の角層のバリア機能を損ない,真皮内の血管網を損傷して出血させるものであるため,細菌やウイルス等が侵入しやすくなり,また,被施術者が様々な皮膚障害等を引き起こす危険性を有しているとして,本件行為が保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為であることは明らかであると判断した上,入れ墨の施術に当たり,その危険性を十分に理解し,適切な判断や対応を行うためには,医学的知識及び技能が必要不可欠である,よって,本件行為は,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるから,「医行為」に当たるというべきであるとの判断を示している。
そして,①入れ墨の施術によって障害が生じた場合に医師が治療を行えば足り,入れ墨の施術そのものを医師が行う必要はない,②被告人が使用していた色素の安全性に問題はなく,入れ墨の施術の際には施術用具や施術場所の衛生管理に努めていたから,本件行為によって保健衛生上の危害が生ずる危険性はなかった,という弁護人の主張に対し,原判決は,入れ墨の施術に伴う危険性や,施術者に求められる医学的知識及び技能の内容に照らせば,上記①の主張は採用できないし,医師法17条が防止しようとする保健衛生上の危害は抽象的危険で足りることから,弁護人が上記②で主張する事情は前記判断を左右しないとして,弁護人の主張を排斥している。
(2) 憲法適合性及び実質的違法性に関する原判決の判断要旨
ア 医師法17条により規制の対象となる医行為とは,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為に限られるという解釈は,同条の趣旨から合理的に導かれ,通常の判断能力を有する一般人にとっても判断可能であると考えられ,同条による処罰の範囲が曖昧不明確であるとはいえないから,医師法17条は憲法31条(罪刑法定主義)に違反しない。
なお,医師法17条をこのように解釈して,成人に対する入れ墨の施術を処罰することは,体系的にみて他の法令と矛盾しない。
イ 医師法17条は,憲法22条1項で保障される入れ墨の施術業を営もうとする者の職業選択の自由を制約するものであるが,医師法17条は国民の保健衛生上の危害を防止するという重要な公共の利益の保護を目的とする規定であり,入れ墨の施術は,医師の有する医学的知識及び技能をもって行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為であるから,医師免許を得た者にのみこれを行わせることは,上記の重要な公共の利益を保護するために必要かつ合理的な措置というべきである。また,このような消極的・察的目的を達成するためには,営業の内容及び態様に関する規制では十分ではなく,医師免許の取得を求めること以外のより緩やかな手段によっては,上記目的を十分に達成できないと認められる。したがって,本件行為に医師法17条を適用することは憲法22条1項に違反しない。
ウ 入れ墨の危険性に鑑みれば,これが当然に憲法21条1項で保障された権利であるとは認められないが,被施術者の側からみれば,入れ墨の中には,被施術者が自己の身体に入れ墨を施すことを通じて,その思想・感情等を表現していると評価できるものもあり,その範囲では表現の自由として保障され得るのであり,その場合,医師法17条は,憲法21条1項で保障される被施術者の表現の自由を制約することになる。しかしながら,表現の自由といえども絶対無制約に保障されるものではなく,公共の福祉のための必要かつ合理的な制約に服する。そして,国民の保健衛生上の危害を防止するという目的は重要であり,その目的を達成するためには,医行為である入れ墨の施術をしようとする者に対し医師免許を求めることは,必要かつ合理的な規制である。したがって,本件行為に医師法17条を適用することは憲法21条1項に違反しない。
エ 人が自己の身体に入れ墨を施すことは,憲法13条の保障する自由に含まれると考えられ,そのため,医師法17条は入れ墨の被施術者の上記自由を制約するものである。しかしながら,上記自由も絶対無制約に保障されるものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を受けることはいうまでもなく,入れ墨の施術に医師免許を求めることは重要な立法目的達成のための必要かつ合理的な手段である。したがって,本件行為に医師法17条を適用することは憲法13条に違反しない。
オ 入れ墨の施術によって保健衛生上の危害を生ずるおそれがあるのであって,施術者及び被施術者にも憲法上保障される権利があるとしても,それが保健衛生上の危害の防止に優越する利益であるとまでは認められない。我が国では,長年にわたり,入れ墨の施術が医師免許を有しない者によって行われてきたが,医師法違反を理由に摘発された事例が多くない,という事情があるにしても,本件行為が,実質的違法性を阻却するほどの社会的な正当性を有しているとは評価できない。したがって,本件行為には実質的違法性が認められる。
以上のとおり,原判決は,憲法違反ないし憲法適合性の欠如,さらには本件行為には実質的違法性がない旨をいう弁護人の主張をいずれも排斥している。
第2 本件控訴の趣意及び主張の概要
本件控訴趣意の要旨は,原判決が,医師法17条の医業の内容である「医行為」を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう」と解釈し,本件行為,すなわちタトゥー施術行為に本条を適用して,被告人を有罪とした原判決の法解釈ないし判断は,刑事裁判の原則である罪刑法定主義に反し,また,憲法が保障する被告人の権利を侵害するものであって,このような解釈に基づく法の適用は許されないのであるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というものである。以下,その主張の概要を示すこととする。
1 「医行為」の意義に関する主張の概要
(1) 「医行為」の意義について
医師法は,医師の資格,業務等を規制する法律であり,同法は,「医療及び保健指導」を医師の任務として定め(同法1条),免許制度等を通じて医療・保健指導を高いレベルに維持することによって,公衆衛生の向上・増進に寄与し,ひいては国民の健康な生活を確保することを目的としている。その目的は,医師に高度の適性,資質を要求するとともに,医師以外の者による「医療及び保健指導」を禁止することによって初めて達成されるものであり,そのために,医師法17条は,医師でない者の医業を禁止し,刑罰をもってこれを担保することとしている。
医師法17条により禁止される無免許医業は,医師の責務である「医療及び保健指導」を侵す行為でなければならないため,まずは,①医療及び保健指導に属する行為であること(医療関連性)という要件が必要となる。もっとも,「医療及び保健指導」に属する行為であれば,直ちに「医行為」であるとすることはできない。医師法17条は,医師の職務の保護を通じて国民の健康を保護するためのものであり,この観点からは,保健衛生上の危険性のある行為をそれに応じた知識・技術がある者によって行わせることが重要であり,危険性に応じた考慮が求められることになる。その結果,医師のように広く深い医学上の知識・技術を習得した者が独占すべき行為というのは,相応の危険性を有する行為に限られることになる。そこで,「医行為」の要件として,②「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生ずるおそれ」という要件が求められる。
医師法及び関連する資格法規は,第一次的に医師に広い業務独占を認め,その上で個々の医療従事者に個別制限的に列挙された範囲での業務を医師の下で行うことを認めるという形をとっている。こうした立法政策からは,保健衛生上の危険性のある行為のうち,社会通念上,医療従事者が通常行う行為をいったんは広く医行為として包摂する必要があることになり,保健衛生上の抽象的な危険のある行為が広く医行為とされることになる。この観点からは医行為の範囲は広く捉えられることになるが,当然,社会通念上の医療関連性は外枠として存在しなければ罪刑法定主義に違反する。ここにいう「社会通念」の判断の際には,当該行為が行われてきた歴史的な経緯,関連法制度,医療従事者の養成課程で学修する内容に含まれるかどうかなどを考慮しなければならない。
以上のとおり,医師法17条の「医行為」というためには,①社会通念上,医療関連性のある行為で,②医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生ずるおそれのある行為であることが必要である。
(2) 「医行為」を巡る学説等
医師法制定当時の立法者の意思としては,医業あるいは医行為とは,「疾病の診断,治療,投薬など」を行うこと,つまり,医療と関連するものであると考えていたことは明らかであり,また,学説においても,初期の通説によれば,(イ)広義の医行為とは,「人に対して医療の目的の下に行われるところの社会通念上この目的到達に資すると認められる行為をいう」と考えられており,(ロ)狭義の医行為とは,「広義の医行為中,医師の医学的知識と技術を用いてするのでなければ生理上危険を生ずるおそれがある行為をいう」と考えられており,医師法17条で「医師でなければ,医業をなしてはならない」という場合の医業は,この狭義の医行為を業とすることを意味すると解されていた。このように,「医療関連性」は当然の前提とされていたのである。
その後,「医行為とは医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為である」とする立場が「現在の通説」とされるようになったが,旧来の通説と「現在の通説」の間に差異を見出すことはできず,学説上,医療関連性のない行為が医行為に当たるかは議論となっていないのであり,医療関連性(広義の医行為性)の脱落は意識的に行われたものではない。
(3) 「医行為」に関する裁判例等
大審院時代の初期の裁判例には「疾病の診察治療」の要素のみに言及するものがあるが,その後,医療関連性に加え,保健衛生上の危険性が一定程度に達していることを要するとする立場が一般化していた。
そして,最高裁昭和30年5月24日第3小法廷判決(刑集9巻7号1093頁)は,患者に対し,聴診,触診,指圧等を行った被告人の行為について,「被告人の行為は,・・・医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは生理上危険がある程度に達していることがうかがわれ,このような場合にはこれを医行為と認めるのを相当としなければならない」と判示したが,この事案では,疾病の治療の性質は問題なく認められるため争点とはならず,もっぱら危険性の多寡のみが問題となった事案であり,その原審の説示内容にも照らせば,①医療関連性,②保健衛生上の危険性が一定程度に達していること,の2つを医行為性の要件とする立場に立ち,事案に即して,争点となった保健衛生上の危険性の程度について言及した判例とみることができる。
そして,その後の最高裁判例(昭和48年9月27日第1小法廷決定(刑集27巻8号1403頁),平成9年9月30日第1小法廷決定(刑集51巻8号671頁))の各事案は,いずれも医療関連性が肯定できる事案である。
2 本件行為の「医行為」該当性について
(1) タトゥー(入れ墨)施術業の医業該当性
我が国において,彫り師という職業は1840年代に確立したとされ,我が国の法制度上,タトゥー(入れ墨)を施術するために医師の資格が必要とされたことはないという歴史的な経緯がある。入れ墨に関して,かつて,警察犯処罰令2条24号という法規制が存在したが,これは社会道徳の維持という趣旨の規定であり,また,現在,地方自治体ごとに青少年保護育成条例により,青少年の保護育成という観点からの規制がなされているが,タトゥー(入れ墨)に関して,医療や保健指導という観点からの規制が及んだ事実はない。さらに,タトゥー(入れ墨)を施すには,保健衛生上の知識だけではなく,施術そのものの手技の習得やデザイン等の美的な要素に関する素養や知識の習得が不可欠であるが,これらは医療従事者の養成課程ではおよそ取り扱われることのないものである。以上に照らせば,社会通念上,タトゥー(入れ墨)施術に医療関連性がないことは明白である。
「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」の観点から検討してみても,タトゥー(入れ墨)施術の際に相応の注意を払えば保健衛生上の危害の多くは防止可能であり,医師でなければ対処することのできないものではない。現に,我が国において保健衛生上の危害はほとんど知られておらず,また,海外主要国では,医師免許ではなく,より取得の容易な資格制度等,緩やかな規制によって足りるとされている。
以上のとおり,医師法17条の合理的な解釈からすれば,タトゥー施術業は「医業」に該当しないと考えるべきである。
(2) 美容整形外科手術等の医療該当性について
以上のような解釈の下,原判決が指摘する美容整形外科手術等の医療該当性が問題となるが,美容整形は,我が国に根付き始めた頃から医師によって担われ,医師の努力と研さんによって発展し,形成外科分野の一分野を構成しつつ,専門分化してきたという歴史的背景を有する。また,関連法制度に照らすと,「美容外科」という診療科目は,昭和53年の医療法改正により,診療標榜科目に追加されているし,医療従事者の養成課程をみても,医学部で美容整形外科に関する教育が行われている。以上によれば,美容整形の分野が,社会通念上,医療関連性を有することは明白である。そして,「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」の観点から検討しても,美容整形外科手術等に伴う保健衛生上の危険性の程度は高度なものであり,医師でなくては防止することができないといえる。
そうすると,美容整形外科手術等は,医療関連性を有し,相応の保健衛生上の危険性を伴う行為であるから,「医行為」に該当する。
原判決は,医療関連性を要求すれば,美容整形外科手術等が「医業」に含まれないことになるとしているが,その判断は誤っている。
(3) 諸外国におけるタトゥーの法規制
諸外国において,タトゥーは医師が行うべき医療行為とは明確に区別され,別個の規制がなされている。こうした諸外国のタトゥーに対する規制の仕方は,タトゥーの施術は医師が行うべきものではなく,医師免許を求めるほどの危険を有するものではないことを示している。また,医師法をもってタトゥー施術業を規制しなければ,タトゥーの施術によって生じる保健衛生上の危害を防止できないか,より緩やかな制限が存在しないかを考えるにあたっても参考にすべきである。
3 医師法17条の憲法適合性について
以上のとおり,医師法17条の合理的な解釈からすれば,タトゥー施術業は「医業」に該当しないと考えるべきであるが,タトゥー施術業に医師法17条を及ぼすとすれば,職業選択の自由(憲法22条1項)や表現の自由(憲法21条1項)等を侵害するものとして適用違憲となると考えざるを得ない。
(1) 憲法22条1項適合性について
ア 原判決の問題点は,医師の免許制が職業選択の自由そのものにとって極めて強力な制限であることを十分に考慮していないところにある。医師の免許制は各種の資格制の中でも極めて強力な制限であることは明らかで,医師免許を要求することはタトゥー施術業にとって禁止的ともいえる制約になる。
本件については,いわゆる薬事法違憲判決(最高裁昭和50年4月30日大法廷判決(民集29巻4号572頁))のいう「より緩やかな制限によってはその目的を十分に達成することができないと認められる」か否かについて,綿密な審査を行うべきである。原判決は,この点について十分な審査を行わず,安易により緩やかな手段の存在を否定したものといわざるを得ない。
イ 医師法17条は,生命・身体に対して一定程度以上の危険性のある行為について,高度な専門的な知識・技能を有する者に委ねることを担保し,医療及び保健指導に伴う生命・健康に対する危険を防止することを目的としている。こうした目的と医師法17条によりタトゥー施術業を規制することとの間に目的・手段の関連性があるかどうかについては,タトゥー施術業は医療・保健指導とはおよそ異なる業務であるから,タトゥー施術業を規制することには,目的と手段との関連性が全くみられない。
ウ タトゥー施術業が,医療・保健指導に関する広く深い専門知識・技能を有する医師という資格を有する者によって行わなければ安全に行われ得ないのかについて,確かに,タトゥーには原判決が指摘するようなアレルギーや感染症等の危険が伴う。しかしながら,原判決には「営業の内容及び態様に関する規制では十分でない」ということの理由が全く示されていない。より緩やかな規制の下でも社会的に許容できる水準の安全性を確保することは十分に可能である。
前記のとおり,タトゥー施術業に医師免許を要求することは,タトゥー施術業にとって禁止的ともいえる強い制約であるところ,タトゥーの施術は,医師免許を要求しなくては社会的に許容できないほどの危険性が生じているわけではない。現状においても,タトゥー施術に関わる事故はほとんど確認されておらず,タトゥー施術の安全性に対する懸念は少なくとも顕在化はしていない。潜在的な危険性については,タトゥー施術には原判決が指摘するようなアレルギーや感染症等の危険が伴うことは確かであるが,彫り師に対して一定の教育・研修を行い(場合によっては,届出制や登録制,医師免許よりは軽易な資格制度の下に置くこと),また,施術設備,器具の衛生状態や施術前後の手順に関する基準に従って相応の注意を払っていれば,危険性は大きく低下するはずである。海外主要国ではタトゥー施術業に医師免許を要求している例はない。
タトゥー施術業に医師免許を要求することはタトゥー施術業に参入することに禁止的といってよい強い制約となる一方で,医師免許を要求しなくても社会的に許容できないほどの危険性が生じているわけではないことから,本件では規制の必要性が否定され,より緩やかな規制手段が存在するとして違憲判断をすべきである。
(2) 被告人の表現の自由との関係での合憲性
ア 原判決は,「入れ墨の危険性に鑑みれば,これが当然に憲法21条1項で保障された権利であるとは認められない」と判示しているが,タトゥーの施術は,人の肌の上にメッセージ文言や絵柄を刻み込むものであって,思想や感情等の表明であるといえ,表現の自由として保障されるものであるといえる。人の肌の上に施術されるという特徴があるが,憲法は「一切の表現の自由」を保障しているのであり,この特徴はタトゥー施術を表現の自由の保護範囲外に置く理由とはならない。タトゥーの施術行為とタトゥーそのものを分けることは妥当でない。被施術者の表現の自由が保障されていても,そのタトゥーを施術する自由が保障されないとすれば,被施術者の表現の自由は,保障されていないのと同じであるからである。タトゥーの施術は,彫り師と被施術者とが共同して行う表現といい得る場合が通常である。
イ 表現規制を目的としていない規制が偶発的に表現の自由の規制に該当する場合には,当該規制の本来の目的との関係での目的手段審査を行い,仮にその観点からは適合性があるとしても,表現の自由を過度に制約する場合には規制は許されないと考えるべきである。
本件は,代替不可能な表現手段について実質的に全面禁止するものであるから,過度な制約として違憲である。
ウ 仮に憲法判断を回避するのであれば,実質的違法性阻却のレベルで,個々の事例の中の個別事情を詳細に検討すべきである。本件では,被告人の施術の技量は熟練したものであったこと,衛生面についても相応の配慮がなされていたこと,依頼者への説明もなされていたこと,健康被害が生じていなかったこと等の個別事情からは,被告人の行為は憲法上保護されるべきものといえ,違法性阻却により無罪とすべきである。
(3) タトゥーの被施術者との関係での合憲性
ア 自己の身体にタトゥーを施すことは,自己の身体に相当の永続性を持った刻印を施すという身体の処分に関する重大な選択であるという側面に着目すると,自己決定権として憲法13条で保障されると考えられる。自己の信念を示す文言であれば第三者にとっても表現であることは明瞭であり,また,文字ではなく絵柄の場合には芸術的表現の自由として保障される。
イ 自己決定権や表現の自由の制約を目的としていない規制であるとしても,それらの自由を制約する場合には,当該規制の本来の目的との関係での目的手段審査を行い,仮にその観点からは適合性があったとしても,自己決定権や表現の自由を過度に制約する場合には規制は許されないと考えるべきである。
本件は,代替不可能な表現手段について実質的に全面禁止するものであり,自己の身体にタトゥーを施す自己決定権も全面的に制約するものであるから,生命・身体への危険の程度に比して過度な制約として違憲である。
ウ なお,仮に自己決定権や表現の自由が生命・身体の安全という重要な保護法益に優越するとは言いにくいとしても,個別の事情によっては実質的違法性の阻却が認められるべきである。自らの身体にタトゥーを施すことによって信念の表明等を行うことは,表現の方法として代替する手段のない貴重な方法であること,彫り師によるタトゥー施術業が禁止的な制約を受けてしまえば,ほかにタトゥーを施す術がないこと,他方,安全性の観点との関係では,本件では被施術者はリスクを理解した上で施術を受けていること,相応の保健衛生上の措置がとられていたこと,これらの事情を考慮すれば,違法性阻却により無罪との結論が妥当である。
本件控訴の趣意及び主張の概要は,以上のとおりである。
第3 当裁判所の判断
当裁判所は,本件行為に医師法17条を適用することは,医師法の解釈適用を誤ったものであると判断した。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるから,原判決は破棄を免れない。
以下,当裁判所の判断内容を詳論する。
1 医師法17条にいう医業の意義について
(1) 医師法17条は,「医師でなければ,医業をなしてはならない。」と規定し,これに違反した者は処罰される。本条は,医師でない者の医業を禁止したものであり,その結果,医師は医業を独占して行うことができることとなる。
ここでいう医業の概念について,医師法は全く規定しておらず,その理由としては,医業の具体的内容が,医学の進歩に伴い変化するものであるから,定義的規定を置くことが困難であり,また妥当でないということが指摘されている。そうすると,「医業とは,医行為を業として行うことである」とした上で,医師法の立法目的等により,医業の内容や限界を見極めながら,医行為を合理的に解釈するのが相当である。
医師法17条の医業の内容である医行為の意義について,「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」という要件,言い換えれば,「医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」という要件(以下「保健衛生上の危険性要件」ということがある。)が必要であることは,検察官と弁護人との間で解釈の相違はなく,原判決も同様に考えており,当裁判所にも異論のないところである。
争いがあるのは,上記要件のほか,上記行為の前提ないし枠組みとして,「医療及び保健指導に属する行為」,すなわち弁護人の主張する「医療関連性」という要件が別途,必要であるか否かである。
この点,従来の学説は,医行為を広義と狭義の2つに分け,広義の医行為とは,医療目的(医師法1条に定められた医師の職分からすれば,「医療及び保健指導の目的」とするのが正確である。)の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものとした上,疾病の治療・予防,出産の際の処置,あん摩,マッサージ,はり,きゅうなど医療目的に適う行為がここに含まれることになり,医師は当然にこれらの行為を業として行うことが認められるが,医師以外にも特定の行為についてその資格を有する者が行うことを認めるものも含まれると解し,他方,医師法17条により医師以外の者が業として行うことが禁じられる狭義の医行為とは,広義の医行為の中で,医師が医学的知識と技能を用いて行うのでなければ人体に危険を生ずるおそれのある行為であり,診療行為に限らず,輸血用の血液の採取,予防接種など医師が行うのでなければ,危険を生ずるおそれのある行為が含まれると解していた。
弁護人の主張する医療関連性の要件は,結局,従来の学説が狭義の医行為について「広義の医行為の中で」という枠組みを設定していたのと同趣旨に帰着すると理解される。これに対し,検察官や原判決は,その後の学説が明示している定義や厚生労働省による行政解釈と同様, 医業の内容である医行為は,保健衛生上の危険性要件があれば足り,「広義の医行為の中で」という枠組み,言い換えれば,医療関連性という要件は不要であると解しているのである。
当裁判所は,医業の内容である医行為については,保健衛生上の危険性要件のみならず,当該行為の前提ないし枠組みとなる要件として,弁護人が主張するように,医療及び保健指導に属する行為であること(医療関連性があること),従来の学説にならった言い方をすれば,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものであることが必要であると解する。その理由は,以下のとおりである。
(2) 医師法は,医療関係者の中心である医師の身分・資格や業務等に関する規制を行う法律であるところ,同法1条は,医師の職分として,「医師は,医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定している。すなわち,医師法は,「医療及び保健指導」という職分を医師に担わせ,医師が業務としてそのような職分を十分に果たすことにより,公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保することを目的としているのである。
この目的を達成するため,医師法は,臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して,医師として具有すべき知識及び技能について医師国家試験を行い,免許制度等を設けて,医師に高度の医学的知識及び技能を要求するとともに,医師以外の無資格者による医業を禁止している。医師の免許制度等及び医業独占は,いずれも,上記の目的に副うよう,国民に提供される医療及び保健指導の質を高度のものに維持することを目指しているというべきである。
以上のような医師法の構造に照らすと,医師法17条が医師以外の者の医業を禁止し,医業独占を規定している根拠は,もとより無資格者が医業を行うことは国民の生命・健康にとって危険であるからであるが,その大きな前提として,同条は,医業独占による公共的な医師の業務の保護を通じて,国民の生命・健康を保護するものである,言い換えれば,医師が行い得る医療及び保健指導に属する行為を無資格者が行うことによって生ずる国民の生命・健康への危険に着目し,その発生を防止しようとするものである,と理解するのが,医師法の素直な解釈であると思われる。そうすると,医師法17条は,生命・健康に対して一定程度以上の危険性のある行為について,高度な専門的知識・技能を有する者に委ねることを担保し,医療及び保健指導に伴う生命・健康に対する危険を防止することを目的としているとする所論の指摘は,正当である。したがって,医師は医療及び保健指導を掌るものである以上,保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であっても,医療及び保健指導と関連性を有しない行為は,そもそも医師法による規制,処罰の対象の外に位置づけられるというべきである。
(3) 検察官や原判決は,保健衛生上の危険性要件のみで足りるという解釈に基づき,本件行為はこの要件を満たすから医行為に当たると結論づけている。確かに,後にみるように,本件行為が保健衛生上の危険性要件に該当することは否定し難い。
しかしながら, 現代社会において,保健衛生上の危害が生ずるおそれのある行為は,医療及び保健指導に属する行為に限られるものではなく,これとは無関係な場面で行われる行為の中でも,いろいろと想定される。そういう状況の下で, 医師法17条の医行為を「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」という要件のみで判断する場合,その危害防止に医学的知識及び技能が求められるか否かの判断が決定的に重要な意味を持つこととなるが,この要件は,理容行為等について本件当事者間でも見方を異にしていることにも表れているように,必要とされる医学的知識及び技能並びに保健衛生上の危害についての捉え方次第で判断が分かれ得るという意味で,一定の曖昧さを残していることは否定できない。そうすると,保健衛生上の危険性要件の他に,大きな枠組みとして医療関連性という要件も必要であるとする解釈の方が,処罰範囲の明確性に資するものというべき
である。
そして,医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生ずるおそれのある行為を全て医師法の対象とすると,社会通念に照らし,医師が行うとは想定し難い行為まで包摂されかねないのであって,そのような解釈の仕方は,前記のとおり,医師法が医師の身分・資格や業務等に関する規制を行う法律であることや,同法1条が,医師には前記のような目的(公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保すること)の下に業務を行うことが期待される旨宣明していることに照らして,妥当とはいえないし,処罰範囲の不当な拡大を招くおそれがあるという意味においても,難点がある。
さらに,現実的な観点からも,そのような行為を全て医師に担わせるということは,不可能といわざるを得ない。やはり,医療及び保健指導という場面を想定して,当該行為の医行為該当性について判断を下すのが相当というべきである。保健衛生上の危害が生ずるおそれのある行為が,医療及び保健指導とは無関係な場面で行われる行為であるときは,必要に応じて,個別に刑法によって処罰し,場合によっては,異なる観点からの法的な規制を及ぼすことも考えられるのである。
(4) 原判決は,医療関連性を要件とすべきであるという弁護人の主張に対し,そのような解釈では,例えば美容整形外科手術等の医行為性を肯定することができない旨説示するが,以下のとおり,首肯し難い。
① 美容整形は,一般に,身体外表の正常部位や老化の現れた部位に対して,外科手術等を施し,より美しくさせ,あるいは若返らせることによって,形態や容姿が原因となる精神的負担を軽減し,個人を社会に適応させる形成外科の一分野といわれ,昭和53年の医療法改正により,診療標榜科名として「美容外科」が追加されている。
美容整形は,所論が指摘するとおり,我が国に根付き始めた当初から医師によって担われ,形成外科医を中心に発展し,形成外科の一分野をなして専門分化してきた背景があり,また,上記医療法の改正当時,既に,美容外科の基礎となる知識及び技術が各大学の医学部において教育され,その他大病院においても研修の機会が多々設けられており,現在でも,医学部で美容整形外科に関する教育が行われている。
ところで,医療とは,現在の病気の治療と将来の病気の予防を基本的な目的とするものではあるが,健康的ないし身体的な美しさに憧れ,美しくありたいという願いとか醜さに対する憂いといった,人々の情緒的な劣等感や不満を解消することも消極的な医療の目的として認められるものというべきである。美容整形外科手術等により,個人的,主観的な悩みを解消,心身共に健康で快適な社会生活を送りたいとの願望に医療が応えていくことは社会的に有用であると考えられ,美容整形外科手術等も,このように消極的な意義において,患者の身体上の改善,矯正を目的とし,医師が患者に対して医学的な専門的知識に基づいて判断を下し,技術を施すものである。
以上からすると,美容整形外科手術等は,従来の学説がいう広義の医行為,すなわち,「医療目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるもの」に含まれ,その上で,美容整形外科手術等に伴う保健衛生上の危険性の程度からすれば,狭義の医行為にも該当するというべきである。したがって,医業の内容である医行為について医療関連性の要件が必要であるとの解釈をとっても,美容整形外科手術等は,医行為に該当するということができる。
② 上記に関連して,検察官は,答弁書において,入れ墨と同様に人の皮膚に針を用いて色素を注入する行為態様であるアートメイクの事案は,これまで多数件が医師法違反として問題なく処罰されているが,これは,入れ墨と同様,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為とされているからであり,このことは既に確立された法解釈といえ,原判決の法解釈・処理と整合するものであると主張する。
アートメイクの概念は,必ずしも一様ではないが,美容目的やあざ・しみ・やけど等を目立ちづらくする目的で,色素を付着させた針で眉,アイライン,唇に色素を注入する施術が主要なものであり,その多くの事例は,上記の美容整形の概念に包摂し得るものと考えられ,アートメイクは,美容整形の範疇としての医行為という判断が可能であるというべきである。後にみるように医療関連性が全く認められない入れ墨(タトゥー)の施術とアートメイクを同一に論じることはできないというべきである。
2 医師法17条の解釈を巡る最高裁判例について
(1) 原判決も指摘し,所論も言及する①最高裁昭和30年5月24日第3小法廷判決(刑集9巻7号1093頁)の事案は,疾病の治療の性質は問題なく認められるため争点とはならず,もっぱら危険性の多寡のみが問題となった事案であり,争点となった保健衛生上の危険性の程度について説示した判例とみることができる。また,同様に,②最高裁昭和48年9月27日第1小法廷決定(刑集27巻8号1403頁)及び③最高裁平成9年9月30日第1小法廷決定(刑集51巻8号671頁)の各事案は,いずれも医療目的で行われる行為で,その目的に副うと認められるものであることが肯定し得る中で,保健衛生上の危険性が問題となった事案ということができ,この点は,原判決も所論もおおむね同様の見方をしている。
ところで,大審院時代の判例をみると,医行為について,疾病の治療,予防等の目的の下に行われ,その目的に副う行為であること,すなわち医療関連性に加え,保健衛生上の危険性が一定程度に達していることを要すると解釈されていたものと考えられ,最高裁の上記各判例もこれと立場を同じくしているものと解される。
すなわち,上記①の最高裁判決の原審である大阪高裁昭和28年5月21日判決(刑集9巻7号1098頁)は,要旨,「医行為とは,人の疾病の治療を目的とし医学の専門的知識を基礎とする経験と技能とを用いて,診断,薬剤の処方又は外科的手術を行うことを内容とするものを指称し,等しく人の疾病の治療を目的とするものであって,たとえば按摩,鍼,灸等の如き療術は医業類似行為の範疇に属し,あん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法による取締の対象となるが医行為とはならない。しかし,被告人の治療方法は,医師でない,医学上の知識と技能とを有しない者が,みだりにこれを行うときは生理上の危険があり,所論の掌薫療法,紅療法とは趣を異にし,むしろ蛭療法同様外科手術の範囲に属する医行為である。」旨説示している。
この原審の判断に対し,最高裁は,要旨,「被告人の行為は,医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは,生理上危険がある程度に達していることがうかがわれ,このような場合には,これを医行為と認めるのを相当とする。」「原審が被告人の行為を外科手術の範囲に属する医行為であるとした説明の当否及び引用した大審院判例の適否は別として,その判断は結論において誤りはない。」旨説示して原判決を支持したものであり,原審の判断に一部留保を付しているものの,上記のような大審院時代の判例及びこれを踏襲したと理解される原審の判断内容の基本的な枠組みを否定したものではない。
また,上記②の最高裁決定の原審である東京高裁昭和47年12月6日判決(刑集27巻8号1411頁)は,要旨,「医師法17条にいういわゆる医業をなすとは,人の疾病の治療,予防等を目的とし,医学の専門的知識を必要とする診断,薬剤の処方,投与または外科的手術を行うことを内容とするいわゆる医行為に従事することを業とすることを意味するものと解される(最高裁昭和30年判決等を引用)。」「被告人の行為は,当該相手の求めに応じてそれらの者の疾病の治療,予防を目的として,本来医学の専門的知識に基づいて認定するのでなければ生理上危険を生ずるおそれのある断食日数等の判断に資するための診察方法というほかなく,問診に当たるから,医行為である。」旨説示し,最高裁は,医行為であることを認めた原判決を支持したのである。
上記③の最高裁決定の原審等においては,医療目的で行われ,その目的に副う行為であることに直接言及はされていないものの,このことを当然の前提とした上で,保健衛生上の危険性が問題となった事案ということができ,上記③の最高裁決定は,争点となった保健衛生上の危険性を認め,医行為であることを肯定した判例と位置づけられる。
このように最高裁判例は,医業の内容である医行為について,保健衛生上の危険性要件のみならず,弁護人が主張する医療関連性,すなわち,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものであることという要件も必要としていると解するのが妥当である。
(2) 原判決は,上記最高裁判例の各事案が,いずれも被告人が疾病の治療ないし予防の目的で行った行為の医行為性が問題となったもので,医行為の要件として上記目的が必要か否かは争点となっておらず,上記各判例はこの点についての判断を示したものではないとし,本件において,医行為の要件として「疾病の治療,予防の目的」が不要であると解しても,最高裁の判例に反しないと説示している。また,検察官も,答弁書において,同様に,上記最高裁判例の各事案では,いずれも,弁護人のいう「医療関連性」が争点となったものではないから,最高裁の各判例が,これを要求しているとまでは結論づけられないと主張する。
しかしながら,疾病の治療,予防等の目的,ひいては,弁護人の主張する医療関連性の要否が争点となっていないからといって,これが医行為の要件として不要であるという解釈が直ちに是認されるものではなく,むしろ大審院以来の判例の流れをみれば,最高裁判例は医療関連性を必要とする立場であると理解するのが妥当であることは,前述のとおりである。
3 本件行為(タトゥー施術)が医師法17条で禁止される医行為に該当するかについて
(1) 既に検討したとおり,医師法17条で禁止される医行為とは,医療及び保健指導に属する行為(医療関連性がある行為),すなわち,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものの中で,医師が行うのでなければ,言い換えれば,医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは,保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であると解するのが相当である。この解釈に基づき,本件行為(タトゥー施術)が医師法17条で禁止される医行為に該当するかについて検討する。
(2) 保健衛生上の危険性要件についてみると,原判決は,本件行為はいわゆる入れ墨であるところ,入れ墨が,必然的に皮膚表面の角層のバリア機能を損ない,真皮内の血管網を損傷して出血させるものであるため,細菌やウイルス等が侵入しやすくなり,被施術者が様々な皮膚障害等を引き起こす危険性を有していること,入れ墨が色素を真皮内に注入するものであることから,アレルギー反応が生じる可能性があること,入れ墨の施術には必然的に出血を伴うため,被施術者が何らかの病原菌やウイルスを保有していた場合には,血液や体液の管理を確実に行わなければ,施術者自身や他の被施術者等に感染する危険性があることを指摘して,本件行為が保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為であることは明らかであると説示する。その上で,原判決は,入れ墨の施術に当たり,その危険性を十分に理解し,適切な判断や対応を行うためには,医学的知識及び技術が必要不可欠であるとして,本
件行為は,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であると判断している。
確かに,本件行為に伴って,原判決が指摘するような保健衛生上の危害を生ずるおそれがあることは否定できず,これに応じて,本件行為の施術者には,施術によって生じるおそれがある感染症やアレルギー反応等,血液や体液の管理,衛生管理等を中心とする一定の医学的知識及び技能が必要とされることも事実であるから,本件行為は保健衛生上の危険性要件を満たすものといえる。
(3) しかしながら,翻ってみると,以下に述べるとおり,本件行為は,そもそも医行為における医療関連性の要件を欠いているというべきである。
すなわち,原審及び当審で取り調べられた関係証拠によれば,入れ墨(タトゥー)は,地域の風習や歴史的ないし風俗的な土壌の下で,古来行われてきており,我が国においても,それなりに歴史的な背景を有するものであり,1840年代頃には彫り師という職業が社会的に確立したといわれている。
我が国では,ある時期以降,反社会的勢力の構成員が入れ墨を入れるというイメージが社会に定着したことなどに由来すると思われるが,世間一般に入れ墨に対する否定的な見方が少なからず存在することは否定できない。他方で,外国での流行等の影響もあって,昨今では,若者を中心にファッション感覚から,あるいは,個々人の様々な心情の象徴として,タトゥーの名の下に入れ墨の施術を受ける者が以前より増加している状況もうかがわれる。そのような中で,入れ墨(タトゥー)を自己の身体に施すことを希望する人々の需要に応えるものとして,タトゥー施術業がそれ相応に存在している。
このように,入れ墨(タトゥー)は,皮膚の真皮に色素を注入するという身体に侵襲を伴うものであるが,その歴史や現代社会における位置づけに照らすと,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義があり,また,社会的な風俗という実態があって,それが医療を目的とする行為ではないこと,そして,医療と何らかの関連を有する行為であるとはおよそ考えられてこなかったことは,いずれも明らかというべきである。彫り師やタトゥー施術業は,医師とは全く独立して存在してきたし,現在においても存在しており,また,社会通念に照らし,入れ墨(タトゥー)の施術が医師によって行われるものというのは,常識的にも考え難いことであるといわざるを得ない。
そして,そもそも,入れ墨(タトゥー)の施術については,その性格上,前記のとおり,感染症やアレルギー反応等,血液や体液の管理,衛生管理等に関する医学的知識や技能は,当然に一定程度必要となろうが,入れ墨(タトゥー)の施術において求められる本質的な内容は,その施術の技術や,美的センス,デザインの素養等の習得であり,医学的知識及び技能を基本とする医療従事者の担う業務とは根本的に異なっているというべきである。この点からも, 医師免許を取得した者が,入れ墨(タトゥー)の施術に内在する美的要素をも修養し,入れ墨(タトゥー)の施術を業として行うという事態は,現実的に想定し難いし,医師をしてこのような行為を独占的に行わせることが相当とも考えられない。
以上によれば,入れ墨(タトゥー)の施術は,医療及び保健指導に属する行為とは到底いえず,医療関連性は認められない。したがって,本件行為は,医師法17条が禁止している医業の内容である医行為には該当しない。
(4) 付言すると,仮に,原判決のように,医療関連性という要件を不要とし,保健衛生上の危険性要件のみで足りるという解釈をとれば,本件行為は医行為に該当し,タトゥー施術業に医師法17条を適用することになる。
しかしながら,このような医師法17条の解釈適用によると,以下に述べるとおり,憲法が保障する職業選択の自由との関係で疑義が生じるのであり,このことからしても,医療関連性を欠くためタトゥー施術の医行為性を肯定することはできないという前記解釈適用の妥当性が支えられているというべきである。
ア 原判決のように,入れ墨(タトゥー)の施術を,医師法17条の医行為に該当すると解釈した場合,医師以外の者が行うことが禁止され,これに違反した者は処罰されて,医師のみが入れ墨(タトゥー)の施術を行うことを許容されるという結果になる。
タトゥー施術業は,反社会的職業ではなく,正当な職業活動であって,憲法上,職業選択の自由の保障を受けるものと解されるから,タトゥー施術業を営むために医師免許を取得しなければならないということは,職業選択の自由を制約するものであり,原判決も,これを前提として判断している。
イ そして,原判決は,職業選択の自由の違憲審査基準について,薬事法違憲判決(最高裁昭和50年4月30日大法廷判決(民集29巻4号572頁))を参照して,「一般に職業の免許制は,職業選択の自由そのものに制約を課する強力な制限であるから,その合憲性を肯定するためには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。
また,それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的・警察的措置である場合には,職業の自由に対するより緩やかな制限によってはその目的を十分に達成することができないと認められることを要する。」と説示しているところ,この説示は正当である。
続いて,原判決は,「医師法17条は国民の保健衛生上の危害を防止するという重要な公共の利益の保護を目的とする規定である。」と説示しており,医療関連性という要件を不要とする原判決の立場によれば,医師法17条の目的について,「医療及び保健指導に伴う生命・健康に対する危険を防止すること」ではなく,上記のように捉えることになろう。
ウ そこで,上記目的を達成するための規制の手段についてみる。
まず,医師を目指す者は,一般的に,大学の医学部で6年間の教育を受け,医師国家試験に合格しなければならず,医師として医療行為等に従事するには医師免許を取得する必要があるなど,医師法が規定する医師の免許制は,各種の資格制の中でも相当に厳しい制限といえる。タトゥー施術業が,医業に含まれ,医師免許を必要とする職業であるとしたならば,入れ墨(タトゥー)の彫り師にとっては禁止的ともいえる制約になることは明らかというべきである。
そして,入れ墨(タトゥー)の施術は,医師が行うのでなければ,言い換えれば,医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは,保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるとはいえ,厳密にみると,そこで必要とされる医学的知識及び技能は,医学部教育や医師国家試験で要求されるほど広範にわたり,かつ,高水準のものではなく,より限られた範囲の基本的なもので足りると考えられる。また,所論が指摘するように,海外主要国においては,タトゥー施術業に医師免許を要求している例は見当たらず,医師が行うべき医療行為とは別個の規制がなされている。そうすると,我が国でも,彫り師に対して一定の教育・研修を行い,場合によっては届出制や登録制等,医師免許よりは簡易な資格制度等を設けるとか,タトゥー施術業における設備,器具等の衛生管理や被施術者に対する施術前後の説明を含む手順等に関する基準ないし指針を策定することなどにより,保健衛生上
の危害の発生を防止することは可能であると思われる。
エ 原判決は,国民の保健衛生上の危害の防止という目的を達成するためには,「営業の内容及び態様に関する規制では十分ではない」という。
しかしながら,以上にみたように,上記目的を十分に達成するため,入れ墨(タトゥー)の彫り師にとっては禁止的ともいえる制約をもたらす医師法による規制が,必要不可欠であるといえるか甚だ疑問であり,医師法の規制対象にするのではなく,より緩やかな規制の下でも社会的に許容できる水準の安全性を確保することは可能と考えられる。タトゥー施術業に伴う保健衛生上の危害を防止するためには,何らかの規制は必要ではあるが,原判決のように,医師法17条で規制の対象となる医行為を医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生ずるおそれのある行為と解釈して,タトゥー施術業が,医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生ずるおそれを伴うものであることを理由に,これを医師法17条の規制対象とする,すなわち,医師免許という厳格な資格制限による医師法の規制を及ぼすことは,他により緩やかな制限が可能であることからすれば,規制の範囲が必要な限度を超えている
ものといわざるを得ない。その意味で,タトゥー施術業を医師法で規制することには,目的と手段との関連において合理性がないというべきである。
オ 以上のとおり, 入れ墨(タトゥー)の施術は医師のみがなし得るとする原判決の解釈適用によれば,タトゥー施術業を営む被告人の職業選択の自由を侵害するおそれがあり,憲法上の疑義が生じるといわざるを得ない。
また,所論は,原判決の解釈適用によれば,職業選択の自由の他にも,タトゥー施術業を行う者の表現の自由,さらに,現実には入れ墨(タトゥー)の施術を行う医師などいないことになり,入れ墨(タトゥー)を自己の身体に施すこと自体を実質的に禁止するに等しいことから,タトゥーを自らの身体に入れる者の表現の自由及び自己決定権を侵害すると主張しているが,これらの点を検討するまでもなく,上記のとおり,タトゥー施術業は,医師法にいう医業に該当しないとの前記解釈適用が妥当である。
(5) なお,当裁判所のように,タトゥー施術業に医師法17条が適用されないという解釈をとると,現状においては,入れ墨(タトゥー)の施術に伴う保健衛生上の危害のおそれに着目したタトゥー施術業自体に対する規制は,存在しないことになる。
しかしながら,入れ墨(タトゥー)の施術に伴う保健衛生上の危害のおそれという問題に対しては,医師法の医行為を拡張的に解釈してこれを処罰対象として取り込むのではなく,必要に応じて,業界による自主規制,行政による指導,立法上の措置等の規制手段を検討し,対処するのが相当というべきである。
結局,医師に入れ墨(タトゥー)の施術を独占させ,医師でない者のタトゥー施術業を医師法で禁止することは,非現実的な対処方法というべきであり,そのような医師法の解釈は合理性,妥当性を有しないといわざるを得ない。
(6) 以上のとおり,結論として,原判決の判断は維持し難く,原判決は破棄を免れない。
第4 結論
以上の次第であるから,刑訴法397条1項,380条により原判決を破棄し,同法400条ただし書により直ちに当裁判所において自判すべきものと認め,更に次のとおり判決する。
本件公訴事実は前記のとおりであるが,被告人の本件所為は医師法17条で禁止される医業に該当するとは認められないのであり,被告人に対する本件公訴事実については罪とならないことになるから,刑訴法336条により被告人に対し無罪の言渡しをすることとして,主文のとおり判決する。
平成30年11月14日
大阪高等裁判所第5刑事部
裁判長裁判官 西田眞基
裁判官 森浩史
裁判官 福島恵子